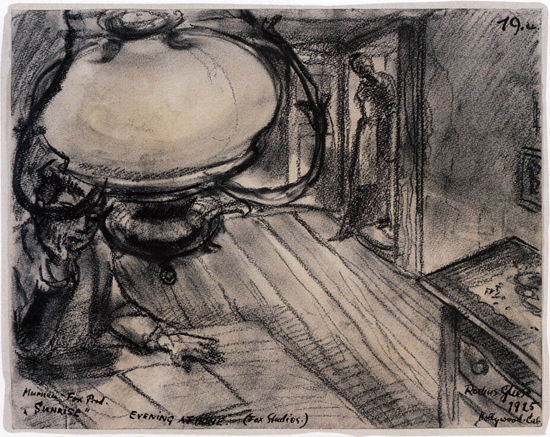Normal
0
0
2
false
false
false
EN-US
JA
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:標準の表;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.5pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:”Century”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Century;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Century;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;}
 |
| アルビン・グラウ |
「海賊ピエトロ」の美術を担当したのは、アルビン・グラウ(1894 – 1971)。ワイマール時代の映画界に「吸血鬼ノスフェラトゥ(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens、1921)」という爆弾を落としていった怪人です。ドレスデン芸術アカデミーで学んだ後、第一次大戦に従軍、戦後はベルリンの頽廃を謳歌した芸術家でした。彼は映画のポスターを手がけたり、各種美術に関わっていたりしましたが、その頃、映画「夜への旅(Der Gang in die Nacht, 1921)」を監督していたF・W・ムルナウと出会います。グラウは、商売人のエンリコ・ディークマンと組んで、映画製作会社プラナ・フィルムを立ち上げたところでした。彼の頭の中には、ブラム・ストーカーの「ドラキュラ」を原作とした吸血鬼映画のアイディアがありました。意気投合した二人は映画化に取り掛かります。 ムルナウが監督、グラウが衣装・美術を担当(そしてプラナ・フィルムが製作)、脚本はヘンリケ・ガリーン、撮影はフリッツ・アルノ・ワーグナー。しかし、公開時にはあまり反響がなかったようです。さらに、ブラム・ストーカーの未亡人に著作権侵害で訴えられ(プラナ・フィルムは版権を確保していませんでした)、映画の上映は差し止め、プリントは焼却するように命じられました。かろうじて焼却をまぬかれた5本のプリントが現在残っており、先年修復されてほぼ完全に近い形まで復元されました。
プラナ・フィルムは「ノスフェラトゥ」一本のみで破産、グラウは再びディークマンと組んで新しい映画製作に乗り出します。その作品がアルトゥール・ロビソンを監督にすえた「恐怖の夜(
Nächte des Grauens)」とこの「海賊ピエトロ」、そしてループ・ピックが監督した「野鴨(
Das Haus der Lüge, 1928)」でした。しかし、これを最後にグラウは映画製作に興味を失います。彼は第一次大戦中からオカルトに異常な興味を持っていて、「ノスフェラトゥ」自体も戦地で聞いた不思議な物語に触発されたものでした。「ノスフェラトゥ」自体はオカルトの要素はむしろ抑制されているのですが、オルロック伯爵からノックへの手紙に見られる奇怪な文字などに、グラウの興味が反映されています。
彼はベルリン・パンソフィア協会(100人以上の会員のいた有名なオカルトの団体)の理事を務めていて、「東方騎士団」の会合にも顔を出していました。1925年に有名なオカルティスト、アルスター・クローリーに出会ってからは、完全にのめりこんでしまいます。ベルリンを中心に積極的に活動し、土星同胞団(
Fraternitas Saturni)のメンバーにもなります。このオカルトへの傾倒が原因で、彼はナチスに追われる身となりました。一部の文献では(
IMDB)、彼は
1942年にブッヘンヴァルト強制収容所で亡くなったことになっています。しかし、
近年の調査で、彼は娘とともにスイスに亡命、
1971年までバイエルン州のバイリッシュツェルで生存していたことがわかっています。晩年は絵を描いて暮らしていたようです。
 |
| 「ノスフェラトゥ」:オカルト文字で書かれた手紙 |
アルノ・フリッツ・ワーグナー(1889 – 1958)。カール・フロイントとならんで、1920年代のドイツ表現主義映画の撮影カメラマンとして最も重要な人物です。彼の作品リストを挙げるだけで、そのままドイツ表現主義の教科書になるような作品群です。
パッション(Madame Du Barry, 1919)エルンスト・ルビッチ 監督
フォーゲルエート城(Schloss Vogeload, 1921) F・W・ムルナウ 監督
死滅の谷(Der müde Tod, 1921) フリッツ・ラング 監督
ノスフェラトゥ(Nosferatu, eine Symphonie des
Grauens, 1922)F・W・ムルナウ 監督
燃ゆる大地(Der brennende Acker, 1922)F・W・ムルナウ 監督
懐かしの巴里(Die Liebe der Jeanne Ney, 1927)G・W・パブースト 監督
スピオーネ(Spione, 1928)フリッツ・ラング 監督
淪落の女の日記(Tagebuch einer Verlorenen, 1929)G・W・パブースト 監督
西部戦線一九一八年(Westfront 1918, 1930)G・W・パブースト 監督
三文オペラ(Die 3 Groschen-Oper, 1931)G・W・パブースト 監督
M(M, 1931)フリッツ・ラング 監督
炭鉱(Kameradschaft, 1931)G・W・パブースト 監督
怪人マブゼ博士(Das Testament des Dr. Mabuse, 1933)フリッツ・ラング 監督
 |
| 「M」撮影中のフリッツ・ラング(左)とアルノ・フリッツ・ワーグナー(右) |
ナチスの政権獲得後も「紅天夢(Amphitryon, 1935)」や「世界に告ぐ(Ohm Krüger, 1941)」などの大作で活躍しています。この頃の彼の作品は「かつての盟友たちが国外に脱出してしまって冴えない」とか「かつてのひらめきが見られない」とか言われることが多いのですが、確かに創造的な仕事は少ないようです。戦後は、ドキュメンタリーなどを撮っていましたが、再起をかけていくつかの映画に参加していたところ、1958年に交通事故で亡くなってしまいました。