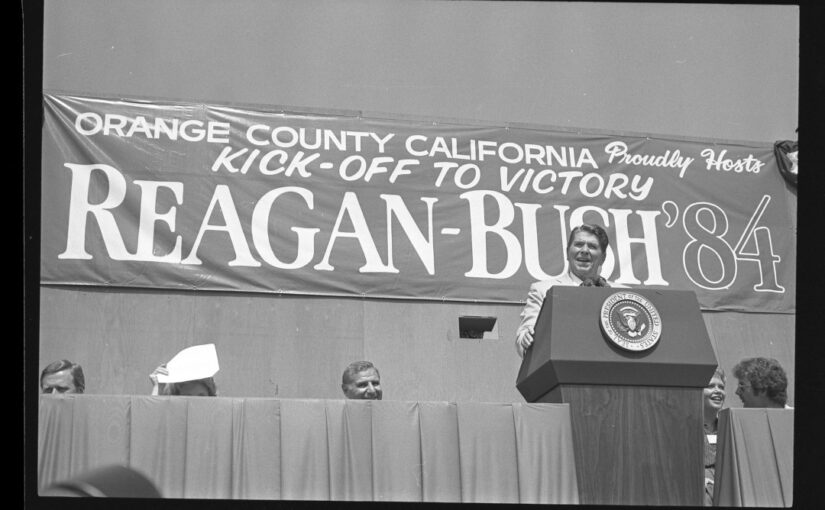自分からの逃走
バーバラ・デミングという名前を聞いてピンとくる人は決して多くないだろう。1960年代後半のベトナム戦争と反戦市民運動について興味がある人であれば、1966年にハノイで非暴力を訴えてデモをした6人組のアメリカ人の一人だったことを覚えているかもしれない。あるいはロバート・スクラーの映画史の著作に、彼女の名前が数回登場するのをぼんやりと記憶している方もいるかもしれない。映画批評の歴史の中で極めて重要な位置を占める、ジークフリート・クラカウアーの「カリガリからヒトラーへ From Caligari to Hitler(1947)」の「緒言 Preface」に、バーバラ・デミングへの謝辞が述べられているのを見て、いったい誰だろうと思った人もいるかもしれない。