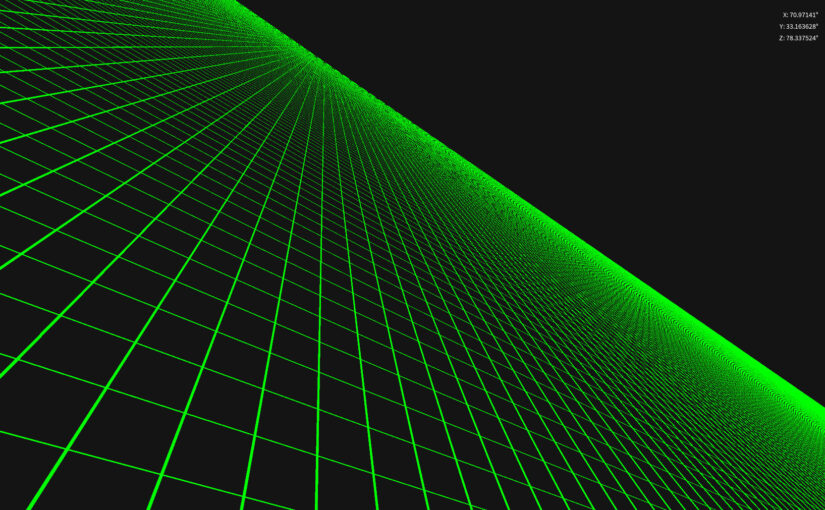わたしたちの果てなき切望 (17)
「四季」派についての吉本隆明の批判から、戸坂潤にさかのぼっていくと見えてくるものは何か。そして、一見矛盾のように見える感性の世界秩序が、実はこの酷い世界をやり過ごすための平面、プロパガンダが機能する平面だということを考えてみる。
同じ万年筆で…
津村信夫の兄で映画評論家の津村秀夫も、1930年代の、室生犀星や他の詩人たちとの邂逅や、弟と同人誌を作っていたころを幸福な時代として記録している。生涯を通じて弟の文筆活動を支援し、没後すぐに詩集を編纂したのも秀夫だった。
そして秀夫自身も、《文学》への憧憬を持ち続け、散文を、そして時には小説を発表していた。
さうして遠く講堂の方からは「荒城の月」だの「靑葉の笛」だのが洩れて來るのを耳にする。その間の氣分が私には堪へがたい嬉しさであつた。段々自分達の出番が近づいて來ると、敎師に引率されて列をつくり暗い廊下を渡つて花壇の方へ行く。講堂は二階である。階下の職員室の横にその花壇がある。そこから、まあ樂屋口といつてもよいやうな階段をのぼつて二階の講堂に行く。春の夜にその花壇のあたりで行列させられてゐると、何んだかわけのわからぬ花の匂ひがした。薄暗いが、人の顔はどうやら判別できる。番組の都合でおほむね五年は五年、六年は六年といふ風に男女の組が引つづいて出演するので、女生徒の列とよく前後したが、さういふ薄暗みの中で、お須美さんの顔を朦朧と發見したりすると私の胸はときめいた。無論、口なぞきけないがただ眺めるだけで、華やかな感じに捉はれた。
津村秀夫
「青春の回想」
戦時中でも、津村秀夫は同人誌「四季」に寄稿していた。「青春の回想」は昭和18年(1943年)に書かれたものである。津村は、この文章を書いたころ、同じ万年筆で「赤十字精神を…描く映画企画が、適切であろうか」とか「大東亞數億の民族の中には…如何に未開民族の多いことであらうか」と書いていた。
私が、理解できない、あるいは心情的に理解しているのだけれども、論理として言語表現に至ることができない、《矛盾》が、この点である。同じ万年筆で「胸はときめいた」と「敵愾心が足りない」と書き綴ることである。同じインクで「ローラーカナリヤの黄色い抜毛も/霜の地面でかすかに渦巻く」と「豚じものアメリカ/血まどへるそこな豚ども/その豚屠れ」と印刷することである[❖ note]❖ローラーカナリヤ/豚じものアメリカ 「ローラーカナリヤ」は阪本越郎の詩「冬の朝」より抜粋、「豚じものアメリカ」は竹村俊郎の詩「豚」より抜粋。 いずれの詩も「四季」昭和17年2月号に掲載された。 。菫と星に目を輝かせつつ、玉砕を唱えたことである。
四季派
戦時中の津村信夫は、軽井沢よりもさらに北の善光寺平、戸隠の地に魅せられ、「戸隠の繪本(1940)」「善光寺平(1945)」を出版している。これらの散文、詩作には、戦争の影はみとめられない。しかし、津村信夫が戸隠に心酔したのも、保田與重郎(1910-1981)の影響といわれ、実際「戸隠の繪本」は保田が編集顧問をつとめる出版社「ぐろりあ・そさえて」から刊行されている。保田は反近代主義、反モダニズムの立場から大日本帝国の拡大路線に反対したとも言われるが、その文章を貫くのは、悲壮感の純度を極度にまで高めた神州不滅の思想である。彼が説く悲壮へのロマンチシズムは、アッツ島の玉砕、特に民間人の玉砕を理想化して、創造性と積極性なるものをそこに見出していた。
アツツのことに對する國民的印象は一言にして申せぬものがあつた。それについて一喜一憂したのは戰況發表過程の現象であつて、玉碎の後の印象は、これを一言には申せぬ。それは通常の敗れたといふ印象ではない。單なる敵愾心ではない。つまり悲劇としての印象でなく、崇高としての印象である。この印象を創造力の面から考へるなら、こゝで玉碎といふもののもつ創造性と積極性が、神のものとして了知せられるであらう。戰の勝敗としてうける印象ではない。はるかに異常な靈的な印象であつた。
保田與重郎 [1]
堀辰雄が特に親しみをよせた立原道造(1914-1939)は、戦争とともに急激に国粋主義に心酔していったが、それを創作として試みる前に病死した。津村信夫は、戸隠に関する著作を残して1944年に病死する。彼らを含む「四季」の代表的な文学者たちが、戦後に「戦争責任」を激しく追及されなかったことは、運命による采配だったのかもしれない。
しばしは『四季』派は政治や戦争とは無関係な優しい詩人たちのようにみられている。それは代表的詩人である中原中也、立原道造、津村信夫、あるいは先師と仰いだ萩原朔太郎らを、戦争激化の前に失ったことにもよる。もし、この詩人たちが存命していたら、戦争詩をつくらなかった保証はない。
栗原克丸 [2 p.139]
戦後、「四季」そして「コギト」「日本浪曼派」の戦時中の位置づけを追究しようとしたのは、吉本隆明(「『四季』派の本質」等)、橋川文三、大岡信らである。吉本隆明は、三好達治を中心にすえて、同じ万年筆がボードレールを翻訳し、戦争詩を書いたことを追究する。
欧米人の実体を「紅毛賊子」とか「めりけんばら」とかいうようなコトバで表現している三好達治が、メリメの訳者であり、ボードレールの訳者であり、西欧の近代文学の昭和における代表的な移植者のひとりであることに注目してみなければならぬ。西欧近代社会の特質と、西欧的な発想について、無知であるはずもない知識人が、太平洋戦争において、封鎖的な無知な排外意識と同等の地点に平然と移行しえた、ということはおどろくべきことである。しかもこれはかならずしも「四季」派の詩人のみの特質ではなかった。日本のインテリゲンチャが、ほとんどひとしなみにたどった発想の経路だったのである。「四季」派の詩人においても、早く死んだ立原道造をのぞいて、すべてこの経路をすすんだのである。
吉本隆明 「『四季』派の本質」[3]
吉本が問題にしたのは、戦争責任といったような、戦争協力、アジテーション、プロパガンダ実践の罪の重さではない。彼は、「四季」派が擬古語、擬古律といった 時代錯誤の先祖かえりを見せた点に注目し、それがモダニズム意識を失いつつ、伝統感性をもって支配体制に順応していくプロセスであることを指摘したのだった。すなわち、抒情的感性の枠組みそのものが、同じ万年筆で花鳥風月と戦争を謳うことを可能にしていたのだ。
しかし、そのような思索は戦後が年を重ねるにつれて、希釈され中和されていったように見える。例えば、学研が1980年に発行した「堀辰雄(人と文学シリーズ. 現代日本文学アルバム)」には、昭和17年3月号の「四季」の目次を見せながら、以下のような説明を添えている。
昭和17年3月号の「四季」の目次 純朴な兵士をうたった詩「三浦のこと」等を除けばここにはわが国が戦時にあることをどこにもうかがうことができない、純文学的雰囲気が全体を貫いている
「堀辰雄」[4 p.205]
本当にそうなのだろうか。その前号の昭和17年2月号の「四季」に竹村俊郎(1896-1944)が書き連ねられた言葉は、果たして世間一般が考える「純文学的雰囲気」をもっていると言えるのだろうか。
殺戮は好まず
破壊は悲しみの極み
されど吾等が建設の行方ことごと
屎まり散し
牙喫み誥べる
豚じものアメリカ
血まどへるそこな豚ども
その豚屠れ
竹村俊郎「豚」
さらに同書では、竹村俊郎の美文調でおとなしい「戦死」を引用しているが、なぜ同時に掲載された「丈夫ごころ(踏み破る幾多離国/切屠る余多の蝦)」を引用しないのか。「四季」及び「四季派」の《純文学的雰囲気》のイメージはそこまでして守らなければならないものなのだろうか。
また、雑誌「四季」は、戦時中に《中原中也賞》を設立し、三回にわたって同人たちに賞を与えている。その受賞者である杉山平一(1914-2012)や平岡潤(1906-1975)が多くの《戦争詩》を発表しているという事実に言及されることは稀である。
海を渡るタイヤ
東支那海を北回歸線を
南へ南へ南下するタイヤ
(私の生れた乳房の里へ)
(私を生んだ魔法の樹林へ)
平岡潤「タイヤ」より
[5 p.218]
兵士の肩の上の銃のごとく
斜めに
朝陽を肩に 進軍する
工場労務者諸君
われらの戦争は長く長く
そして最後の雌雄を決するのは
遂にきみらの手であるだろう
杉山平一「工場労務者に」
1942年
[6]
杉山平一は、尼崎精工創立者の杉山黌一の息子で、戦時中すでに尼崎精工の株を保有し専務となっていた。尼崎精工は高射砲の信管を主製品とし、軍需工場として指定されていた。また、国家総動員法のもと、聾唖者の雇用を積極的に進めたことで評価されている。杉山平一は、戦時中の詩や散文に、この工場での出来事を散りばめている。しかし、会社の専務が詩人で「ざツさツ さツさツ/あゝその規律と きみらの質朴の人生こそ/われらの日本を救ふのだ」という詩を工員達に向けて送るという閉塞的な奇怪さは、当時の工員たちの目にはどのように映ったのだろうか。
「四季派」というのは、戦後の長い間の蔑称で、つい最近も、ある同人誌に「四季派」は、お涙頂戴の詩をかき、戦争に加担し、など、おきまりの口真似で片づけている文章を見たが、おそらく、その人々は井伏鱒二から桑原武夫らを擁した「四季」を見てもいないのだろう。
その広い顔ぶれにもかかわらず、主催者だった堀辰雄の上品な雰囲気が全体を包んでいたのも間違いはない。
杉山平一 1995年[7]
また「四季」の中核メンバーのひとり、神保光太郎(1905-1990)は「ナチス詩集(昭和16年刊)」を編纂した。出版社は前述の「ぐろりあ・そさえて」である。この詩集はフリードリッヒ・シュナック(Friedrich Schnack, 1888-1977)、ヴィル・ヴェスパー(Will Vesper, 1882-1962)、ヘルマン・クラウディウス(Hermann Claudius, 1878-1980)ら、ヒトラーに忠誠を誓った詩人たちの作品を集めたものだった。訳者は富士川英郎(1909-2003、のち東京大学教授ドイツ文学)、高橋義孝(1913-1995、九州大学及び名古屋大学教授ドイツ文学)、野島正城(1909-1997、東京大学教授ドイツ文学)、近藤圭一、瀧田勝(1912-1985、茨城キリスト教短期大学教授)、山田新之輔の6人である。いずれも東京帝国大学のドイツ文学卒の学者、教育者たちである。ちなみに同じく東京帝国大学独文科卒でドイツ留学もした高橋健二(1902-1998)は、ナチス文学を積極的に日本に紹介し、岸田国士の後任として昭和17年(1942年)に大政翼賛会宣伝部長になっている。
これら、ナチスの文学を日本に積極的に紹介した人々は、戦後、リルケ(富士川)、トーマス・マン(高橋義孝、野島)、シラー(野島)、ケストナー(高橋健二)の権威として知られるようになる。
プロパガンダが機能する平面
戸坂潤(1900-1945)は、自由主義と日本的ファシズムを論ずる際の要として、《文学的自由主義(文学主義)》という概念を用いた。彼は自由主義哲学を以下のように説明する。
自由主義思想が一つの独自な論理を有つことによって哲学体系にまで組織される時、夫は広く自由主義哲学と呼ばれてよいものになるのであるが(尤もその多くのものはそういう命名法に満足しないことは判っている)、この哲学体系の根本的な特色は、その方法が多少に拘らず精練された「解釈の哲学」だということにある。事物の現実的な秩序に就いて解明する代りに、それに対応する意味の秩序に就いてだけ語るのが、この哲学法の共通な得意な手口なのである。例えば現実の世界では、宇宙は物理的時間の秩序に従って現在の瞬間にまで至っている。よく云われることであるが、意識の所有者である人間や(他の生物さえ)がまだ存在しなかった時にも、すでに地球が存在した、ということを地質学と天文学とが証明している。処が自由主義的論理に立つ解釈の哲学は、宇宙のこうした現実の秩序(物理的時間)を問題とはしない、その代りに人間と自然との関係を、人間の心理的時間の秩序に於て問題にしたり、或いは超人間的な又は超宇宙的な従って又超時間的な秩序(そういう秩序は意味の世界に於てしかあり得ない)に於て問題にしたりしかしない。現実の世界に就いて語るように見せかけて、実際に聞かされるのは、意味の(だから全く観念界にぞくする)世界に就いてでしかない。そういうことが世界の単なる解釈ということなのである。
戸坂潤「日本イデオロギー論」
そして、観念論、解釈哲学のなかで最も自由主義哲学らしく振舞うのが《文学的自由主義乃至文学主義》で、これは「文化的に尤もらしく又進歩的に円滑にさえ見せるために工夫し出されたメカニズム」「現実に就いてのファンタスティックな表象である処の文学的な表象乃至イメージを利用して、この文学的表象乃至イメージをそのまま哲学的論理的概念にまで仕立てたもの」にほかならない、と指摘する。戸坂は、盧溝橋事件が起きた、まさしくその時に、極めて辛辣に、《文学主義》の社会的意味を定義する。
現代日本の文化現象に於ける文学主義運動は、陰に陽に、色々様々のニュアンスを以て、大衆の一定層に普及している。小商人、小ブル低級インテリにはファシズムを、之に対して小ブル高級インテリには文学主義を、というのがマルスの神の配当計画なのである。
戸坂潤「日本イデオロギー論」
加藤周一が《新しき星菫派》を批判するなかで「その教養が彼の父親の戰時利得を待つて始めて可能であつたと云ふことを理解しない靑年」と呪詛したのも理解できる。
日中戦争中の戸坂の批判は、戦後の吉本の「四季」派の分析と通底するものがある。戸坂が「意味の秩序」と呼ぶものを、吉本はさらにおし進めて「感性の秩序」と呼んだ。日本の戦争は、世界の在り方の意味さえ解体したのだ。日本の哲学者や文学者たちがめざした近代の超克は、結局、時代錯誤の先祖かえりを生んだにすぎない。
「玉碎あるのみ」と「セザール・フランクの音樂を愛し『冬の旅』の 樂譜をどうにか歌ふこと」、南京陥落の旗行列と『オーケストラの少女』、オラドゥール゠シュル゠グラヌの虐殺と『さようなら、フランツィスカ!』、小津の「かうした支那兵を見てゐると、少しも人間と思へなくなつて来る」と「大變いゝ氣持で『三平の一生』を讀ましていたゞいたことを覺えてゐます」、そして「映画戰」と「お須美さん」── 私は、この思考/嗜好の分裂 ─ 強迫と弛緩、殺戮と星菫、苛烈と静寂、侵略と内向 ─ こそが、プロパガンダが機能する平面をなす軸なのだと思う。なぜなら「現実の世界」はあまりにも酷く、世界は「意味の世界」、そしてさらには「感性の世界」でのみ咀嚼可能だからだ。《果てなき切望》によって痛点を麻痺させることで、今起きている地獄をやり過ごし続ける ── そのやり過ごした先が《死》であるという認識さえ、やり過ごすことができる。
プロパガンダは何のためにあるのか。プロパガンダは、民衆に犠牲を強いるためにある。ぼんやり家で過ごしているだけであれば、決してやらないようなことを、外に出て行ってやるように仕向けるためにある。知らない土地に住む、まったく知らない人間を、憎しみ、殺すように仕向けるためにある。銃弾を受けるただの肉片になることを《栄光》として喜んでやらせるためにある。
プロパガンダは、すべてを提供しなくてもよい。地獄をやり過ごし続ける平面さえ見つければよいのだ。あとは一人一人が《果てなき切望》をみずから見つけてくる。
中村光夫氏が書いて居られたが、氏が戦死した海軍予備学生の手紙を整理した時、そのほとんど全部が堀辰雄の愛読者なのに驚いた、ということである。ぼくもそういった一人だった。人生から断たれ、死に隣りあっていた軍隊生活のなかで、どんなにぼくは堀辰雄の文学を愛したことだろう。そこに現実を逃避している弱い者の感傷があったかもしれない。が、死がほとんど手に触れるような確実さで迫っている時、しかも生への願いが切なく燃えている時、その感傷は果たして逃避という言葉で尽くされるものかどうか。多くの予備学生が堀辰雄を愛読したことは予備学生たちの弱さを示すよりは、死の世界のなかになお生を輝かしく支える強さが堀辰雄の文学にあったことを一層多く語っているように思われる。
矢内原伊作 [8 pp.202-203]
References
[1]^ 保田與重郎, “玉碎の精神” 遞信協會雜誌, no. 422, pp. 10–13, Oct. 1943.
[2]^ 栗原克丸, “日本浪曼派・その周辺 : 文学者の戦争賛美はいかに準備されたか” 高文研, 1985.
[3]^ 吉本隆明, “「四季」派の本質” 吉本隆明全集, vol. 5, 晶文社, 2014, pp. 258–272.
[4]^ 佐多稲子, 涌田佑, 小久保実, 杉野要吉, 谷田昌平, “堀辰雄.” 学研研究社, 1980.
[5]^ “國民詩選 昭和十八年版” 興亞書局, 1943.
[6]^ 杉山平一, “工場労務者に” 四季, no. 66, pp. 36–37, Jun. 1942.
[7]^ 杉山平一, “宛名は先か後か” 詩学, vol. 50, no. 11, p. 53, Nov. 1995.
[8]^ 矢内原伊作, “文学論集 (矢内原伊作エッセイ③).” 雄渾社, 1970.
KINOMACHINAをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。