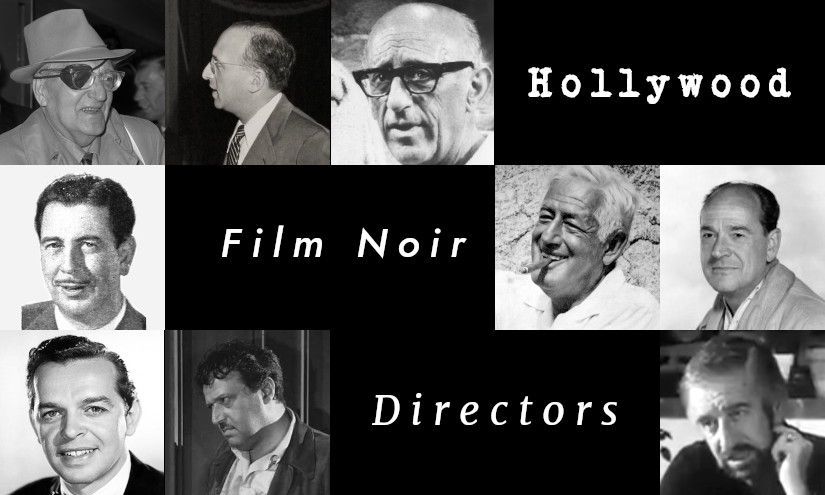Directors and Film Noir
フィルム・ノワールを代表する映画監督と言えば、どんな名前が思い浮かぶだろうか?
おそらく、フリッツ・ラング、ロバート・シオドマク、それにアンソニー・マン、ジョセフ・H・ルイス、エドガー・G・ウルマーといった監督の名前を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。もちろん、オーソン・ウェルズ、アルフレッド・ヒッチコック、ビリー・ワイルダーといった《ハリウッドの巨匠》も、フィルム・ノワールを手掛けた映画監督として忘れてはならないだろう。人口に膾炙している作品を並べてみたとき、これらのハリウッド監督が当然のように列挙されるはずだ。
しかし、果たして実際のところはどうなのだろうか?ロバート・ シオドマクは確かに『幻の女』『殺人者』『裏切りの街角』といった映画ばかり撮っていたような気もするが、本当に多かったのだろうか?ウルマーと言えばパッと『危険なまわり道』が思い出され、その他にもPRCやモノグラムで何か撮っていたと思うのだが、そんなにフィルム・ノワールばかり作っていたのだろうか。
あるいは、フィルム・ノワールと呼ばれる一群の映画をどこの映画スタジオが量産したのだろうか?当時としては、PCAからにらまれることも多い、一般的には不健全とみなされる種類の映画を、積極的に製作していたのは、実際にはどこのスタジオだったのだろう。
そこで、実際に統計を取ってみることにした。なるべく、定量的に、なおかつ網羅的にデータを集めたい。いろいろ検討したうえで、IMDBのデータを利用することにした。IMDBのサイトからデータをダウンロードし、《Film Noir》のタグが付いている映画を抽出、その公開年、監督、出演者、撮影監督、製作会社、配給会社などのデータをクエリできるデータベースを作成した1)。
この方法に問題があるとすれば、《Film Noir》というタグが信用できるのか、という点であろう。IMDBに記載されているデータは、IMDBのContributorたちが付与したり、削除したりしている。確かにこれらのデータに誤りが見つかることもあるが、ごくまれだ。非常によくメンテナンスされていると思う。タグが信頼できない最大の理由は、どの映画を《Film Noir》と呼ぶかは極めて主観的な判断が入ってきてしまうという点だ。もともと定義のあいまいなものを相手にしているのだから、「入っているべきあの映画がカウントされていない」「この映画は《Film Noir》と呼んでいいのか」といった異論や反対意見は必ず出てくるだろう。だが、IMDBでは、多くの場合、複数のタグが1つの映画につけられており、《Film Noir》的性格をもつものにはおおよそ付与されていると思ってい良い。つまり、多くの人が《フィルム・ノワール》だと思っているのにリストから漏れている、というケースよりも、「そういわれれば、《フィルム・ノワール》的な部分もあるかもしれない」といったケースの方が多い。これは、いったんデータを集計してみて、分析しながら取捨選択していくのが良いと思う。問題は、後で見るように、「定義のあいまいなもの」の分析は、フィルム・ノワールと呼ばれる映画についての歴史的事実を追っているのか、それとも歴史的事実について事後的に分類したプロセスをなぞっているだけなのか、結局わからないままなのである。
このIMDBのデータを分析して感じたのは、私自身、自分の先入観が邪魔をして、探求することをおろそかにしてた領域がいかに多くあるか、ということだ。私は「ランダム・ノワール」というもう一つのブログで、フィルム・ノワール作品をなるべく偏りなく選出して論じるということを試みたが、ランダムでもなんでもなかった。ものすごくバイアスのかかったセレクションで50本を論じていた。このデータ分析で初めて知ることになる映画、初めて気づいた領域が実に多くある。それを見ていきながら、今までの認識を改めていきたい。
データ分析:全体の傾向
実際にデータを集計してみると、《Film Noir》のタグがついた映画は991本にのぼる。このうち、ハリウッド製作の映画は947本である。このリストをみて最初に気づくのが、IMDBで《Film Noir》というタグをつける基準が《製作年》で決められている、という点である。1927年から1958年のあいだの作品にだけ《Film Noir》のタグが付けられているのだ。この点は、IMDBのContributorたちの間で合意されているのだろう[❖ note]❖ノワールのタグと製作年 例えば、ポランスキーの有名な《ネオ・ノワール》映画『チャイナタウン(Chinatown, 1974)』には、《Conspiracy Thriller》《Hard-boiled Detective》《Period Drama》《Psychological Drama》などのタグが付いているが、《Film Noir》のタグは付与されていない。 。この結果から察するに《Film Noir》の定義として、「ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督の『暗黒街(Underworld, 1927)』からオーソン・ウェルズ監督の『黒い罠(Touch of Evil, 1958)』まで」という時代による定義が採用されているように思われる。一般的には『三階の見知らぬ男(Stranger on the Third Floor, 1940)』あるいは『マルタの鷹(The Maltese Falcon, 1940)』が始まりとされることが多いが、それ以前の、いわゆる《プロト・フィルム・ノワール Proto-Film Noir》も含めている点が特徴的だ。
年代順に追っていくと、フィルム・ノワールと呼ばれる映画の隆盛期が1946から51年、そして1955から57年に現れているのが分かる。しかし、この傾向をどう分析するべきか、隆盛期は歴史的事実なのか、それともフィルム・ノワールというものを事後的に見出したことによるものなのか、はっきりしなくなってくる。
|
|
|
フィルム・ノワール:公開本数の推移
1927年から1958年まで年毎の公開本数。ピークは1950年、77本のフィルム・ノワールが公開されている。
|
このグラフを見ていて一つ浮かび上がってくるのは、《フィルム・ノワール》の製作を左右する重要な因子として、プロダクション・コードの存在があるのではないか、という見方だ。PCAによるプロダクション・コードの運用に何らかの変化が起きたときに、《フィルム・ノワール》と呼ばれる映画の製作に影響が出るように見える。ジョセフ・ブリーンがPCAに着任してコードの運用強化が実施される直前の1932年に作品数の若干の増加がみられるのは(あるいはブリーンが着任して運用が強化されて作品数が減少するのは)、まさしくプロダクション・コードの影響によるものだろう。《フィルム・ノワール》の映画製作が1944年から活発になるのも、戦争の激化とともにコードの運用が変化せざるを得なくなったことに起因している。その変化をとらえて登場したのが『深夜の告白(Double Indemnity, 1944)』『ブロンドの殺人者(Murder, My Sweet, 1944)』『受取人不明(Address Unknown, 1944)』、少し遅れて『真昼の暴動(Brute Force, 1947)』といった映画群だった。1954年にブリーンが引退して、後任のジェフリー・シューロック(Geoffrey Shurlock, 1894-1976)が後任をつとめ始めた時期に、フィルム・ノワールの2回目の波が来ている。これはシューロックの方針がややリベラルだったというだけでなく、ヨーロッパからの輸入映画や独立製作のエクスプロイテーション・フィルムが氾濫し、プロダクション・コードが実質的に骨抜きにされ始めた時期でもあった。
しかし、プロダクション・コードだけでは製作公開本数の増減を説明できない。他の要因もつぶさに見ていくことにしたい。
フィルム・ノワールの監督たち
まずは、フィルム・ノワールの製作本数の多い監督から見てみたい。下表が「フィルム・ノワールを数多く作った監督」トップ9である*)。
| 順位 | 監督 | 本数 |
| 1 | フリッツ・ラング(Fritz Lang, 1890-1976) | 16 |
| 2 | ウィリアム・バーク(William Berke, 1903-1958) | 15 |
| 3 | ロバート・シオドマク(Robert Siodmak, 1900-1973) | 12 |
| 3 | ジョージ・ブレア(George Blair, 1905-1970) | 12 |
| 5 | ウィリアム・キャッスル(William Castle, 1914-1977) | 11 |
| 6 | アンソニー・マン(Anthony Mann, 1906-1967) | 10 |
| 6 | ジョセフ・ぺヴニー(Joseph Pevney, 1911-2008) | 10 |
| 8 | ヒューゴ・ハース(Hugo Haas, 1901-1968) | 9 |
| 8 | ドン・シーゲル(Don Siegel, 1912-1991) | 9 |
Film Noirのタグがついた映画を最も多く監督したのは、誰あろう、フリッツ・ラングだった。全部で16本の監督作品にFilm Noirのタグがついている。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1936 | 激怒 | Fury | MGM |
| 1937 | 暗黒街の弾痕 | You Only Live Once | United Artists |
| 1938 | 真人間 | You and Me | Paramount Pictures |
| 1943 | 死刑執行人もまた死す | Hangmen Also Die! | United Artists |
| 1944 | 飾窓の女 | The Woman in the Window | RKO |
| 1944 | 恐怖省 | Ministry of Fear | Paramount Pictures |
| 1945 | スカーレット・ストリート | Scarlet Street | Universal Pictures |
| 1946 | 外套と短剣 | Cloak and Dagger | Warner Bros |
| 1947 | 扉の蔭の秘密 | Secret Beyond the Door... | Universal Pictures |
| 1950 | ハウス・バイ・ザ・リバー | House by the River | Republic Pictures |
| 1952 | 熱い夜の疼き | Clash by Night | RKO |
| 1953 | ブルー・ガーディニア | The Blue Gardenia | Warner Bros |
| 1953 | 復讐は俺に任せろ | The Big Heat | Columbia Pictures |
| 1954 | 仕組まれた罠 | Human Desire | Columbia Pictures |
| 1956 | 口紅殺人事件 | While the City Sleeps | RKO |
| 1956 | 条理ある疑いの彼方に | Beyond a Reasonable Doubt | Warner Bros |
フリッツ・ラングの場合、1930年代の《プロト・フィルム・ノワール》が3本もタグ付けされている。一方で『マンハント(Man Hunt, 1941)』がタグ付けされていない。今回の議論では、《プロト・フィルム・ノワール》を対象に含めるなど、すべての条件を同じにして考察したいので、表の結果をそのまま採用しておくが、この2点は注意しておきたい。
だが、第2位はおそらく誰も予想しなかったのではないだろうか。ウィリアム・バーク、15本がリストされている。彼の作品については後で分析するが、『狂騒の町(Roaring City, 1951)』『通り魔(The Mugger, 1958)』の2本がリスト入りしていない。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1944 | ─ | Dark Mountain | Paramount Pictures |
| 1944 | ─ | Dangerous Passage | Paramount Pictures |
| 1944 | ─ | The Falcon in Mexico | RKO |
| 1946 | ─ | The Falcon's Adventure | RKO |
| 1947 | ─ | Shoot to Kill | Screen Guild Productions |
| 1948 | ─ | Waterfront at Midnight | Paramount Pictures |
| 1949 | ─ | Arson, Inc. | Lippert Picttures |
| 1949 | ─ | Sky Liner | Lippert Picttures |
| 1949 | ─ | Treasure of Monte Cristo | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | Danger Zone | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | Pier 23 | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | F.B.I. Girl | Lippert Picttures |
| 1957 | ─ | Four Boys and a Gun | United Artists |
| 1957 | ─ | Street of Sinners | United Artists |
| 1958 | ─ | Cop Hater | United Artists |
3位はロバート・シオドマクとジョージ・ブレアが同数12本で並んだ。シオドマクはお馴染みの映画監督である。監督作品リストを見ても頷ける内容だと思う。『らせん階段(Spiral Staircase, 1946)』はリスト入りしていない。また、シオドマクは1950年以降は、すっかりノワール的な作品を作らなくなっている。彼がヨーロッパに戻ったからだ。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1942 | ─ | Fly-By-Night | Paramount Pictures |
| 1944 | 幻の女 | Phantom Lady | Universal Pictures |
| 1944 | クリスマスの休暇 | Christmas Holiday | Universal Pictures |
| 1944 | 容疑者 | The Suspect | Universal Pictures |
| 1945 | ハリー叔父さんの悪夢 | The Strange Affair of Uncle Harry | Universal Pictures |
| 1946 | 殺人者 | The Killers | Universal Pictures |
| 1946 | 暗い鏡 | The Dark Mirror | Universal Pictures |
| 1947 | ─ | Time Out of Mind | Universal Pictures |
| 1948 | 都会の叫び | Cry of the City | 20th Century Fox |
| 1949 | 裏切りの街角 | Criss Cross | Universal Pictures |
| 1949 | 血塗られた情事 | The File on Thelma Jordon | Paramount Pictures |
| 1950 | ─ | Deported | Universal Pictures |
ジョージ・ブレアはリパブリック・ピクチャーズ専属の監督である。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1944 | ─ | End of the Road | Republic Pictures |
| 1948 | ─ | Madonna of the Desert | Republic Pictures |
| 1948 | ─ | Homicide for Three | Republic Pictures |
| 1949 | ─ | Post Office Investigator | Republic Pictures |
| 1950 | ─ | Unmasked | Republic Pictures |
| 1950 | ─ | Federal Agent at Large | Republic Pictures |
| 1950 | ─ | Women from Headquarters | Republic Pictures |
| 1950 | ─ | Destination Big House | Republic Pictures |
| 1950 | ─ | Lonely Heart Bandits | Republic Pictures |
| 1951 | ─ | Insurance Investigator | Republic Pictures |
| 1951 | ─ | Secrets of Monte Carlo | Republic Pictures |
| 1952 | ─ | Woman in the Dark | Republic Pictures |
次は、ウィリアム・キャッスルが11本で4位だった。キャッスルは、ユニヴァーサルとコロンビアで低予算のエクスプロイテーション色の強い映画を監督しているが、これらのなかにFilm Noirとタグ付けされる作品が数多くあった。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1944 | ─ | The Whistler | Columbia Pictures |
| 1944 | ─ | When Strangers Marry | Monogram Pictures |
| 1944 | ─ | The Mark of the Whistler | Columbia Pictures |
| 1945 | ─ | Voice of the Whistler | Columbia Pictures |
| 1946 | ─ | Mysterious Intruder | Columbia Pictures |
| 1949 | ─ | Johnny Stool Pigeon | Universal Pictures |
| 1949 | ─ | Undertow | Universal Pictures |
| 1951 | ─ | The Fat Man | Universal Pictures |
| 1951 | ─ | Hollywood Story | Universal Pictures |
| 1955 | ─ | New Orleans Uncensored | Columbia Pictures |
| 1956 | ─ | The Houston Story | Columbia Pictures |
アンソニー・マンとジョセフ・ペヴニーが10本で6位に並んだ。アンソニー・マンはリパブリック、PRC、イーグル゠ライオンと渡り歩いた後、MGMへ移籍、1950年代は西部劇が主流となる。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1944 | 夜のストレンジャー | Strangers in the Night | Republic Pictures |
| 1945 | グレイト・フラマリオン | The Great Flamarion | Republic Pictures |
| 1945 | 午前2時の勇気 | Two O'Clock Courage | RKO |
| 1946 | 仮面の女 | Strange Impersonation | Republic Pictures |
| 1947 | 必死の逃避行 | Desperate | RKO |
| 1947 | 偽証 | Railroaded! | PRC |
| 1947 | Tメン | T-Men | Eagle-Lion Films |
| 1948 | 脱獄の掟 | Raw Deal | Eagle-Lion Films |
| 1949 | 国境事件 | Border Incident | MGM |
| 1949 | サイド・ストリート | Side Street | MGM |
ジョセフ・ペヴニーもおそらく日本ではほぼ無名と言ってよい映画監督だろう。フィルム・ノワールではないが『千の顔を持つ男(Man of a Thousand Faces, 1957)』が有名で、日本でもDVDが発売されていたようだが、《フィルム・ノワール》の監督としては認識されていないと思う。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1950 | 恐喝の報酬 | Shakedown | Universal Pictures |
| 1950 | ─ | Undercover Girl | Universal Pictures |
| 1951 | ─ | Iron Man | Universal Pictures |
| 1952 | ─ | Because of You | Universal Pictures |
| 1954 | ─ | Playgirl | Universal Pictures |
| 1955 | 六つの橋を渡る男 | Six Bridges to Cross | Universal Pictures |
| 1955 | ─ | Female on the Beach | Universal Pictures |
| 1956 | ─ | Congo Crossing | Universal Pictures |
| 1957 | ─ | Istanbul | Universal Pictures |
| 1957 | ─ | The Midnight Story | Universal Pictures |
同点8位にヒューゴ・ハースとドン・シーゲルが名を連ねた。ドン・シーゲルは1950年代の作品が中心で、日本でもほぼ全作品紹介されている。一方、ヒューゴ・ハースは全く紹介されていない。非常に対照的な2人の監督である。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1951 | ─ | Pickup | Columbia Pictures |
| 1951 | ─ | The Girl on the Bridge | 20th Century Fox |
| 1952 | ─ | Strange Fascination | Columbia Pictures |
| 1953 | ─ | One Girl's Confession | Columbia Pictures |
| 1954 | ─ | Bait | Columbia Pictures |
| 1954 | ─ | The Other Woman | 20th Century Fox |
| 1955 | ─ | Hold Back Tomorrow | Universal Pictures |
| 1956 | ─ | Edge of Hell | Universal Pictures |
| 1957 | ひき逃げ殺人事件 | Hit and Run | United Artists |
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1946 | ビッグ・ボウの殺人 | The Verdict | Warner Bros |
| 1949 | 仮面の報酬 | The Big Steal | RKO |
| 1953 | 暗黒の鉄格子 | Count the Hours! | RKO |
| 1954 | 第十一号監房の暴動 | Riot in Cell Block 11 | Republic Pictures |
| 1954 | 地獄の掟 | Private Hell 36 | Filmmakers Releasing Organization |
| 1956 | 暴力の季節 | Crime in the Streets | Allied Artists |
| 1957 | 殺し屋ネルソン | Baby Face Nelson | United Artists |
| 1958 | 殺人捜査線 | The Lineup | Columbia Pictures |
| 1958 | 裏切りの密輸船 | The Gun Runners | United Artists |
ここでは、日本であまり取り上げられてこなかった二人の映画監督、ウィリアム・バークとジョセフ・ペヴニーをピックアップしてみたい。
ウィリアム・バーク
|
|
|
『4人の少年と銃(1957)』
オープニング・クレジット。少年たちは強盗を計画している。
|
ウィリアム・バーク ── どれだけの映画ファンがフィルム・ノワール映画監督として彼の名を挙げるだろうか。私は、「ファルコン」シリーズの、どちらか言えばパッとしない続編を見たことがあるだけだった。しかし、その彼の作品をいま一度《フィルム・ノワール》のレンズを通して見なおしてみる必要がありそうだ。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1944 | ─ | Dark Mountain | Paramount Pictures |
| 1944 | ─ | Dangerous Passage | Paramount Pictures |
| 1944 | ─ | The Falcon in Mexico | RKO |
| 1946 | ─ | The Falcon's Adventure | RKO |
| 1947 | ─ | Shoot to Kill | Screen Guild Productions |
| 1948 | ─ | Waterfront at Midnight | Paramount Pictures |
| 1949 | ─ | Arson, Inc. | Lippert Picttures |
| 1949 | ─ | Sky Liner | Lippert Picttures |
| 1949 | ─ | Treasure of Monte Cristo | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | Danger Zone | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | Pier 23 | Lippert Picttures |
| 1951 | ─ | F.B.I. Girl | Lippert Picttures |
| 1957 | ─ | Four Boys and a Gun | United Artists |
| 1957 | ─ | Street of Sinners | United Artists |
| 1958 | ─ | Cop Hater | United Artists |
バークはパラマウント、RKO、コロンビアで低予算映画をひたすら監督し続けていた「B映画の神様」だった。リチャード・フライシャーは、バークを反面教師として自分の監督する作品を選ぶようになった、と自伝に書いている。
バークは「B級映画の神様」として知られていた。何年ものあいだ、撮影スケジュールがたったの10~12日、製作費がたったの10万ドル、そしてスターなんか誰も出ていない映画を作り続けていた。ポストプロダクションの編集とかいった面倒事は全部任せて、1年に8本とか10本とか監督していた。彼は頭がヘンになりそうになっていた。バークはしょっちゅうスタジオのトップ連中に大きな映画をやらせてくれと頼んでいた。50日とか、60日とかの撮影スケジュール、例えば70万ドルとか、80万ドルとか、そういった派手な製作費で、スターが出ている映画を撮りたがった。だが、彼は無視され、ずっと「12日間の驚異」と呼ばれた低予算映画を作り続けていた。
ようやく、仲の良かった友人がRKOで重要なポストに就いた。バークはこの友人をつかまえて、大きな仕事をやらせてくれと頼み込んだ。十分な撮影期間と人気のスターさえいれば、大当たりを作れると彼は確信していた。同情した友人は、バークにチャンスを与えた。撮影スケジュールも長く、スターも出ているA級映画を監督する機会をついに勝ち取ったのだ。しかし、結局バークはその映画をたった12日間で撮ってしまった。
Richard Fleisher [1 p.47]
だが、この話は、フライシャーが自身の置かれた境遇を説明するために、オチを用意して脚色した物語のように思える。ウィリアム・バークはRKOで7本監督しているが、該当する「大きな仕事」、すなわち「A級映画」が見当たらないのだ。唯一『Betrayal from the West (1945)』 が上映時間82分でプログラム的には長編だが、内容的にも、出演者の顔ぶれを見ても、とてもA級映画として企画されたものではない。ただし、このフライシャーの話は、バークの監督作品をとりまく製作環境の描写としては参考になる話であろう。彼の監督作品の大部分は70分を超えることがなく、二本立ての添え物として作られた映画である。1947年以降はリッパート・ピクチャーズやセキュリティ・ピクチャーズというエクスプロイテーション映画専門の独立製作会社で、ノワール犯罪映画だけでなく、冒険活劇、西部劇といったジャンル映画を量産している。彼は多くの映画で製作と監督の両方を兼ね、いい意味でも悪い意味でも、一貫して独特の特徴を備えた低予算映画を作り続けていた。多くの独立製作映画関係者がそうであったように、バークもやがてはTV番組制作と演出に仕事を切り替えていく。
そのような低予算映画を量産するためだけに特化した製作環境の作品のなかでも『Danger Zone (1951)』『Roaring City (1951)』『Pier 23 (1951)』の3作 ─主人公の名前をとって《オブライエン・シリーズ》と呼ぼう─ は特筆に値する。製作・配給はリッパート・ピクチャーズ、ロバート・L・リッパート(Robert Lenard Lippert, 1909 – 1976)がおこした低予算映画専門の映画会社である。この頃、リッパートが試みていたのは、当時急速に普及し始めたテレビを映画の市場として取り込むというアイディアだった。特に、《オブライエン・シリーズ》は、30分のTV放送枠に収まるように最初から念頭に置いて製作されている。それぞれは、上映時間もほぼ1時間であり、定額レンタル専用の二本立ての添え物として十分機能する映画である。だが、内容的には30分のストーリーが2本連続して収められていて、真ん中でカットすると、30分のプログラムが2本できるようになっている。映画館では60分の映画として公開し、テレビ局には30分ものの番組2本として提供する、という仕掛けである。果たして、この公開フォーマットがどこまで成功したのかは判然としないが、この3本以外に「60分の映画゠30分のTV番組×2」というフォーマットを採用しているものを見たことがないところを見ると、あまりうまくいかなかったのであろう。
|
|
|
『23番埠頭(Pier 23, 1951)』
マイク・マズルキ(左)とヒュー・ビューモント(右)
|
リッパート・ピクチャーズは《オブライエン・シリーズ》の3本すべてを、1951年4月から5月のわずか1ヶ月のあいだに公開した。製作と監督のクレジット(Produced and Directed by)は、ウィリアム・バークである。
《オブライエン・シリーズ》は、ヒュー・ビューモント演じるデニス・オブライエンという私立探偵的キャラクターが主役のハードボイルド犯罪映画である。舞台はサンフランシスコのベイエリア、オブライエンはここで起きる凶悪犯罪に巻き込まれ、警察やギャングに追われながら事件の真相を暴いていくという、いささか使い古された様式の物語だ。散発的にロケーション撮影が差し込まれるが、それ以外は安いセットでほとんど仕上げられている。映像のイディオムとして、当時流行だったキアロスクーロを取り入れた視覚的スタイルを一部踏襲しているものの、全体的にはフラットな照明で、むしろ当時のテレビの製作品質に近い。このシリーズのフィルム・ノワール的特徴を挙げるとすれば、それはハードボイルド文体特有の諧謔的なセリフがふんだんに盛り込まれている点である。
ブルガー刑事 いいな、部下にお前を尾行させるからな!
オブライエン お前の部下なんか、象がバスケットボール・コートを歩いているのさえ尾行できないじゃないか。
Pier 23 (1951)
《オブライエン・シリーズ》2作目の『Roaring City』の冒頭、「サンフランシスコの埠頭は大きさがバラバラで、まるで安酒場のコーラス・ガールのラインダンスを見ているようだ」などというボイスオーバーのセリフは、雑誌「ブラックマスク」の短編小説の一節のようだ。だが、これは大衆小説/パルプ小説から直接影響を受けたというよりも、いったんラジオを経由して取り入れられたものである。ハリウッドの映像作品の脚本の歴史を考えるうえで、小説などの文芸作品からの影響だけでなく、ラジオ・ドラマ経由で流れ込んできたスタイル、テクニック、メソッドの模倣についても俯瞰する必要がある。《オブライエン・シリーズ》はまさしくその例であって、サンフランシスコのラジオ局KGOで放送された、ジャック・ウェッブ主演、リチャード・L・ブリーン脚本のラジオ・ドラマ「Pat Novak, for Hire (1946-1949)」、そしてロサンゼルスで制作された姉妹編「Johnny Madero, Pier 23」が、実質的な原作2)である。
1950年代後半になると、バークは、フィリップ・ヨーダンとシドニー・ハーモンの製作会社、セキュリティ・ピクチャーズ Security Picturesで青少年犯罪を題材にした犯罪映画、そしてエド・マクベインの「87分署シリーズ」の映画化を手掛けた。『Four Boys and the Gun (1957)』と『Street of Sinners (1957)』は、当時流行していた青少年非行映画(ジュヴェナイル・デリンクエインシー映画、Juvenile delinquency movies)[❖ note]❖青少年非行映画 1950年代中盤に少年非行をセンセーショナルに扱った映画が人気となり、特に低予算映画やTVドラマが量産された。流行の発端は『暴力教室(Blackboard Jungle, 1955)』『理由なき反抗(Rebel Without a Cause, 1955)』だろう。当時、流行し始めたロックンロールなどの音楽、クルーザーからホットロッドまで若者に人気の自動車、デニムやスウィング・スカートに代表されるファッションなどの風俗を盛り込んで、むしろティーンエイジャーの購買意欲を促すような演出が突出していた。 の好例だろう。『Four Boys and the Gun』(実のところ、少年と呼ぶには年を取り過ぎているのだが)は、強盗殺人事件を起こした4人の少年が、どのようにしてその事件に至ったかを一人一人追っていく、フラッシュバック構造の映画だが、現実にはあり得ないショッキングなラストを含めて、ポットボイラーとしては、比較的長く記憶に残る作品である。『Four Boys and the Gun』『Street of Sinners』のオープニングは、夜の汚れた街のストリートを背景に、派手なビッグバンドジャズが鳴り響くというスタイルで、これはセキュリティ・ピクチャーズのトレードマークだったのだろう。同じくセキュリティ・ピクチャーズが製作に関わっている『ビッグ・コンボ(The Big Combo, 1955)』もこのオープニングスタイルになっている点は注目したい。
エド・マクベインの「87分署シリーズ」の初映画化作品だった『Cop Hater (1958)』、そしてリストには載っていない(i.e. IMDBで《Film Noir》のタグが付いていない)『The Mugger (1958)』は、ウィリアム・バークの遺作となった。小説が発表されてから2年で映像化に至っている。どちらも製作費は最小限で、セットや美術は極めて経済的、ロケーション撮影は皆無に近く、スターは出演していない。もはや残っている数も少なくなってきた独立系映画館での二本立て用として作られた映画だ。果たして製作費を回収できたのかどうかさえ疑問だ。
ウィリアム・バークは、彼の映画がたどった道のりを見る限り、映画監督兼プロデューサーとして、極めて退屈な映画を作り続け、全米で急激に存在価値を失いつつあった独立系映画館のスクリーンをなんとか埋めるという役割を果たした、と言える。彼が《Film Noir》の映画監督として名を連ねるのは、あくまで当時流行していたテーマやスタイルを最大公約数的に還元して、手早く、数多く映像化したからである。ハードボイルドな私立探偵ドラマが流行すれば、それを矢継ぎ早に映像化して、TV番組に入れ込もうとする。少年非行映画が流行すれば、リアリティのないプロットでも構わず安く早く映画化する。彼が1952年から56年のあいだ、フィルム・ノワールと呼ばれる映画を作っていないのも、上のグラフが示すように業界全体が、ノワール的な作風を敬遠した時期と重なっている。この時期、彼はTVに仕事の軸足を移し、西部劇(『The Range Rider (1951-1953)』)や反共スパイ・サスペンス(『The Hunter (1952-1954)』『I, Spy (1955-1956)』)などを手掛けていた。彼のような映画監督やプロデューサーがいたからこそ、様々なスタイルが陳腐化し、クリシェとなって、流行し、廃れていくのである。私はそれが悪いことだとは思っていない。むしろそのようなプロセスを経たからこそ、映像のイディオムとして《フィルム・ノワール》が認識されているのだと思っている。
|
|
|
『Street of Sinners (1958)』
オープニング。暗い夜のストリートを背景にした、サンセリフ/ゴシック字体の装飾を排した感触のタイトルが、警察権力の腐敗と犯罪集団との癒着の物語にふさわしい。
|
ジョセフ・ペヴニー
ジョセフ・ペヴニーの場合は、ウィリアム・バークとは全く対照的な環境で、映画を監督していた。彼はユニバーサルに雇われた監督であり、下表に挙げられたすべての映画をユニバーサルで作っている。
| 製作年 | タイトル | 原題 | 配給 |
| 1950 | 恐喝の報酬 | Shakedown | Universal Pictures |
| 1950 | ─ | Undercover Girl | Universal Pictures |
| 1951 | ─ | Iron Man | Universal Pictures |
| 1952 | ─ | Because of You | Universal Pictures |
| 1954 | ─ | Playgirl | Universal Pictures |
| 1955 | 六つの橋を渡る男 | Six Bridges to Cross | Universal Pictures |
| 1955 | ─ | Female on the Beach | Universal Pictures |
| 1956 | ─ | Congo Crossing | Universal Pictures |
| 1957 | ─ | Istanbul | Universal Pictures |
| 1957 | ─ | The Midnight Story | Universal Pictures |
ペヴニーは俳優として1940年代に登場する。彼が出演した作品は『ボディ・アンド・ソウル(Body and Soul, 1947)』『深夜復讐便(Thieve’s Highway, 1949)』など、すべて《フィルム・ノワール》で、すでにこの時点で彼のテイストが決まっていたと言えるのかもしれない。
ペヴニーが最初に監督したのは『恐喝の報酬(Shakedown, 1951)』である。特ダネ写真を撮るためなら、どんなことでもするカメラマンの名声と成功への道のりから劇的な最期までを描いた、いわゆる卑劣漢の物語で、実際、撮影中のタイトルは『The Magnificent Heel』だった。原作はナット・ダリンジャーとドン・マーティンの「The Red Carpet」とリストされている。ナット・ダリンジャーはハースト・シンジケートのカメラマンで、「黄金期」のハリウッド・スターたちを撮り続けた。 おそらくダリンジャーの話を、ストーリーの形にまとめたのがドン・マーチンだろう。
主人公の報道カメラマン、ジャック・アーリー(ハワード・ダフ)は、決定的に何か ──世間一般にはモラルと呼ばれるかもしれないが、それ以上の何か根本的な、人間が本来兼ね備えているべき、エンパシーとか、理解とか、そういったもの── が欠けており、それが彼自身の無軌道な上昇志向と相まって、関わった者たちの世界の秩序を乱していく。登場人物たちは、煉獄で審判を待っているかのような逆さ吊りの状態のまま、解き放たれる暴力の歯車につぶされていく。ジャックの欲望の対象となる女性が、ファム・ファタールでも聖なる救済者でもなく、物語が進むにつれてジャックとの関係をやがて縮退させて、何も残さないという点も、他の《フィルム・ノワール》とは違う後味を残す。
|
|
|
『恐喝の報酬(Shakedown, 1951)』
報道カメラマン、ジャック・アーリー(ハワード・ダフ)はどんな非道な手を使ってでもスクープ写真を撮ろうとする。この新聞の1面を飾った写真は、ギャングのボス(ブライアン・ドンレヴィー)のクルマに爆弾が仕掛けられているのを知りながら、むしろカメラや照明を準備して、その爆発の瞬間を撮影したものである。
|
一方、同じ年に公開された『Undercover Girl (1951)』も、曖昧さという点で際立っている。父親をギャングに殺された主人公の女性警官のクリス(アレクシス・スミス)は、組織犯罪捜査の決め手の証拠を集めるために、潜入捜査官となる。クリスは、シカゴの犯罪組織から派遣された「サル・ウィリス」として、父親を殺した犯罪組織と接触を始めるのだが、このクリス/サルの二重人格的な設定が、ある種のコスプレのように機能して、見る者を当惑させる。さらにクリスは、警官としての責務と、娘としての復讐心のあいだで揺れている。その揺れ、曖昧さ、どっちつかずの展開が、意図的なのか、それとも演出/演技の失敗なのか、正直分からない。おそらく後者なのだと思うのだが、出来上がった映画としては、その曖昧さだけが奇妙な印象を残す。特にサルになったときのクリスの感じているであろう解放感が、どこか真正の感情のように感じられるのだ。フィルム・ノワールは、多様な曖昧さの次元で機能するが、『Undercover Girl』は、その典型と言ってもよいかもしれない。
|
|
|
『Undercover Girl (1951)』
潜入捜査官(アレクシス・スミス:右)とギャングたちの麻薬の取引現場
|
|
|
|
六つの橋を渡る男(Six Bridges to Cross, 1955)
現金強盗のシーン。
|
1955年に公開された『六つの橋を渡る男(Six Bridges to Cross, 1955)』は、この時期のペヴニーの監督作品のなかでも、最も野心的な作品だ。原作はボストン・グローブ紙の記者、ジョセフ・F・ディニーンの“They Stole $2,500,000 – And Got Away with It”だが、これは1950年1月27日に起きたブリンクス強盗事件を下敷きにしたフィクションである。
脚本はシドニー・ベーム。『高い壁(High Wall, 1947)』『復讐は俺にまかせろ(The Big Heat, 1953)』『恐怖の土曜日(Violent Saturday, 1955)』などのフィルム・ノワール作品の脚本を数多く手掛けている。
この作品では、主人公のジェリー・フロレアを演じた2人の俳優が極めて深い印象を残す。まずティーンエイジャー時代を演じたのがサル・ミネオ(1939-1976)で、これがデビュー作だ。そして成人してからのジェリーはトニー・カーチス(1925-2010)が演じている。この2人は、見た目の特徴がそこまで似ているわけでもなく、それぞれの俳優としてのスクリーンでの印象はかけ離れていると思うのだが、この映画では成長していく1人のキャラクターとして不思議な一貫性がある。二人の演技力もさることながら、演出に一貫性があるからだろう。ただ、この一貫性というのが、曖昧さに満ちた一貫性なのだ。このジェリーという男は、極めて曖昧な存在だ。彼の心理的な主軸がどこにあるのか判然としない。警官/刑事のギャラガーに対して、何を求めているのか、あるいは求めていないのか、ウソをついているのか、それとも本気なのか、悔いているのか、演技なのか。スクリーンに映っている像、聞こえてくる声だけではまったく判断できない。観客はジェリーの笑顔をチャーミングだと感じてよいのか。彼がしおらしい顔をするとき、それは心の底から更生しようと願った末の表情なのか。『恐喝の報酬』『アンダーカバー・ガール』も、似たような曖昧さが全体に漂っていたが、ここでの曖昧さは徹底している。ジェリーは、最後まで明白さを拒んでいる。だからこそ(おそらくプロダクション・コードに従わざるをえなかった)ラストシーンは、残念に感じられてしまうのかもしれない。
強盗事件を想起させるタイトルにも関わらず、実際の強盗のシーンは極めて静かで、盛り上がりをあえて避けている。最小限のアクションとドラマで、むしろ物足りないと感じる観客も多かったのではないか。
『六つの橋を渡る男』はほぼ全編ボストンでロケ撮影された。撮影監督は『裸の町(The Naked City, 1947)』のウィリアム・H・ダニエルズである。オープニングのタイトルバックに流れる歌は、サミー・デイヴィス・ジュニアによるもの。もともとギャラガーの役はジェフ・チャンドラーにオファーされたが、それをチャンドラーが拒否、スタジオから謹慎処分を受けていた。その彼がタイトル曲の作詞をしたうえで、歌手のサミー・デイヴィス・ジュニアに声をかけたのだった。1954年11月19日、サミー・デイヴィス・ジュニアはこの曲の録音のためにラス・ベガスからロサンゼルスのユニヴァーサル・スタジオに向かう途中、事故に遭い、その事故がもとで左眼を失った [2]。
『The Midnight Story (1957)』も、全編ロケーション撮影だが、こちらは舞台がサンフランシスコである。『Undercover Girl』と同じく、個人的な動機に突き動かされて、殺人事件の潜入捜査をおこなう物語である。結末をどうとらえるかは、いろんな意見があるだろうが、中盤部までの、曖昧で不安定な主人公の状況が興味深いだけに、物足りなさを感じるのは否めない。
ジョセフ・ペヴニーの《フィルム・ノワール》作品に共通して言えることは、ユニヴァーサルという比較的恵まれた製作環境が、彼独特の曖昧さに満ちた物語を空中分解から救ったのではないか、ということだ。特に撮影監督の存在は大きいように思える。特にカール・E・ガスリー(『Undercover Girl』『Iron Man』『Play Girl』)、ウィリアム・H・ダニエルズ(『六つの橋を渡る男』『Istanbul』)、ラッセル・メティ(『Because of You』『Midnight Story』)らの貢献は非常に素晴らしい。
今後は、ウィリアム・キャッスル、ヒューゴ・ハースなどの監督も見ていきたい。
Notes
1)^ 当初、IMDB Non-Commercial Datasetsを利用して、《Film Noir》のタグで抽出した結果をもとに解析していたが、正確に抽出されていない映画が相当数あることが判明した。結局、IMDBウェブサイト上で《Film Noir》のタグをもつ映画の一覧を表示させ、それを転記してリストを作成した。そこから上記データベースと突き合わせて、IMDBのIDを取得、抽出されたIDをもとに各データベース間でクエリをかけて、製作年、タイトル、監督、撮影監督、出演者などをCSVで出力した。ただし、アメリカでの公開日と製作会社及び配給会社はこのデータセットに含まれていないので、別途取得する必要があった。CinemagoerというIMDBのScrapingをおこなうツールで、アメリカ公開日は取得できたが、会社名は取得できないことが判明し、IMDBから会社名のデータを直接抽出することはあきらめた。結局IMDBのサイトの検索フィルタで会社名を入力して一覧を表示させ、それを転記してCSVのデータと突き合わせた。このデータ処理は、PythonとExcelを使用しておこなった。
2)^ 「Pat Novak, for Hire」シリーズを生み出したのは、ジャック・ウェッブとリチャード・L・ブリーンであるが、ウェッブのほうは、このあと「ドラグネット(Dragnet)」シリーズの中心人物として活躍する。「ドラグネット」シリーズは、警察の捜査活動を追うセミドキュメンタリー作品で、これもラジオから始まり、その後すぐにTVシリーズに展開された。ウェッブのボイスオーバーが、刑事たちの日々の格闘を淡々とドライに描き出す、そのスタイルが一世を風靡した。「Pat Novak, for Hire」のハードボイルドなボイスオーバーからは遠く離れ、シニカルなジョークやコメントは全くない。「ドラグネット」シリーズは大人気となったが、おそらくハードボイルドなスタイルを採用しなかったことが大きいのではないか。
リー 私の名前はリー・アンダーウッド。300ドルでしてもらいたいことがあるの。1時間ほどで済む仕事よ。
ノヴァック 殺人の依頼じゃないとしたら、ずいぶんといい報酬だな。殺人の依頼だったら安すぎる。
リー 怖いの?
ノヴァック 金をもらって人を殺すのがいやなのさ。俺が捕まったら高くつくぜ。
リー 殺しなら、自分でするわ。ノバックさん、ある人を怖がらせてもらいたいの。
ノヴァック
友達にやってもらえないのか?友達はみんなハンサムすぎるのか?「Pat Novak, for Hire」
第11話 ディキシー・ギリアン
*)^ 『Film Noir』とタグ付けされた映画を5本以上作った映画監督は以下の通り。
| 監督 | 本数 | |
| フリッツ・ラング | Fritz Lang | 16 |
| ウィリアム・バーク | William Berke | 15 |
| ロバート・シオドマク | Robert Siodmak | 12 |
| ジョージ・ブレア | George Blair | 12 |
| ウィリアム・キャッスル | William Castle | 11 |
| アンソニー・マン | Anthony Mann | 10 |
| ジョセフ・ペヴニー | Joseph Pevney | 10 |
| ヒューゴ・ハース | Hugo Haas | 9 |
| ドン・シーゲル | Don Siegel | 9 |
| フレッド・F・シアーズ | Fred F. Sears | 8 |
| ヴィンセント・シャーマン | Vincent Sherman | 8 |
| フィリップ・フォード | Philip Ford | 8 |
| ルー・ランダース | Lew Landers | 8 |
| サム・ニューフィールド | Sam Newfield | 8 |
| ルイス・サイラー | Lewis Seiler | 8 |
| ヘンリー・ハサウェイ | Henry Hathaway | 8 |
| マイケル・カーティス | Michael Curtiz | 8 |
| フィル・カールソン | Phil Karlson | 8 |
| ジョセフ・H・ルイス | Joseph H. Lewis | 8 |
| リチャード・フライシャー | Richard Fleischer | 7 |
| ゴードン・ダグラス | Gordon Douglas | 7 |
| ジョージ・シャーマン | George Sherman | 7 |
| アンドリュー・ストーン | Andrew L. Stone | 7 |
| R・G・スプリングスティーン | R.G. Springsteen | 7 |
| ジョン・ファロー | John Farrow | 7 |
| テッド・テツラフ | Ted Tetzlaff | 7 |
| ルイス・アレン | Lewis Allen | 7 |
| ニコラス・レイ | Nicholas Ray | 7 |
| ロバート・フローリー | Robert Florey | 6 |
| ジーン・ネグレスコ | Jean Negulesco | 6 |
| ロバート・ワイズ | Robert Wise | 6 |
| ジャック・ターナー | Jacques Tourneur | 6 |
| エドワード・L・カーン | Edward L. Cahn | 6 |
| ジョン・スタージェス | John Sturges | 6 |
| アルフレッド・ヒッチコック | Alfred Hitchcock | 6 |
| フェリックス・E・ファイスト | Felix E. Feist | 6 |
| ステュアート・ハイスラー | Stuart Heisler | 6 |
| フランク・タトル | Frank Tuttle | 6 |
| W・リー・ワイルダー | W. Lee Wilder | 6 |
| ジョセフ・フォン・スタンバーグ | Josef von Sternberg | 6 |
| ジョセフ・M・ニューマン | Joseph M. Newman | 6 |
| ウィリアム・ディターレ | William Dieterle | 6 |
| ハリー・ケラー | Harry Keller | 6 |
| オットー・プレミンジャー | Otto Preminger | 6 |
| エドワード・ドミトリク | Edward Dmytryk | 5 |
| D・ロス・レダーマン | D. Ross Lederman | 5 |
| ジョセフ・ケイン | Joseph Kane | 5 |
| アーヴィン・ピシェル | Irving Pichel | 5 |
| エドガー・G・ウルマー | Edgar G. Ulmer | 5 |
| リチャード・ソープ | Richard Thorpe | 5 |
| ウィリアム・キーリー | William Keighley | 5 |
| ジョン・ブラーム | John Brahm | 5 |
| バッド・ベティカー | Budd Boetticher | 5 |
| マクスウェル・シェーン | Maxwell Shane | 5 |
| フィル・ローゼン | Phil Rosen | 5 |
| エドウィン・L・マリン | Edwin L. Marin | 5 |
| ウィリアム・クレメンス | William Clemens | 5 |
| ルドルフ・マテ | Rudolph Mate | 5 |
| レジナルド・ル・ボルグ | Reginald Le Borg | 5 |
| アーチー・メイヨ | Archie Mayo | 5 |
| ジョン・ラインハート | John Reinhardt | 5 |
References
[1]^ R. Fleischer, “Just Tell Me When to Cry.” Carroll & Graf Publishers, 1993.
[2]^ “Sammy Davis Jr. Suffers Eye Injury,” The San Bernardino County Sun, p. 19, Nov. 20, 1954.
KINOMACHINAをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。