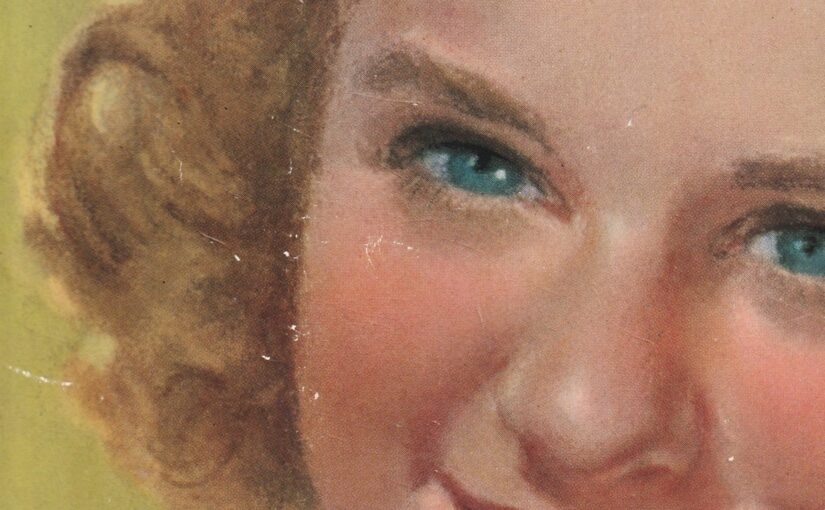わたしたちの果てなき切望 (11)
内田:とにかくヴエニスの映畫展などでは日本映畫が一番汚いでせう
川添:はつきり云ふと汚いです
歐洲映畫界土産話 [1]
盧溝橋事件以降の輸入文化の変化
日本にとって、1937年(昭和十二年)から1938年(昭和十三年)という時期は歴史の転換点だった。盧溝橋事件が起きたのが1937年の7月、それが第二次上海事変へとエスカレートし、12月には南京戦(と虐殺)、翌1938年には徐州会戦と続き、わずかの期間に全面戦争に突入、拡大した。日本国内でも、1938年4月1日に国家総動員法が公布され、国民の生活が国家の統制下におかれる。ここから太平洋戦争まで3年、敗戦まで7年である。
前年に日独伊防共協定が締結されており、ドイツ、イタリアは同盟国として位置付けられていた。これを契機に、独伊と文化的な接近を試みようとする動きがあり、文化人や芸能人も協力している。ヒトラーユーゲントが8月に来日して、日本各地を訪問している[2]。北原白秋はすっかりナチスに感化されていて「萬歳ヒットラー・ユーゲント」という歌の歌詞を書いている。ヒトラーユーゲントが軽井沢に滞在したときには、東宝がユーゲントのメンバーを迎えて映画『牧場物語(1938)』の上映会を催し、原作者の林房雄らが東京から駆けつけ、軽井沢在住の川端康成が会のために奔走したようである[3]。
林房雄はプロレタリア作家としてデビューしたが、投獄されたのち、転向を表明。その後、小林秀雄、武田麟太郎、川端康成らと同人誌「文学界」を創刊。戦争協力を惜しまず、『牧場物語』も3人の帰還兵を主人公とした「戦線銃後」というテーマで映画のために書き下ろされた小説である。
一方、宝塚少女歌劇団は1938年11月から翌年1月まで欧州を訪問し、ポーランド、ドイツとイタリアで計25公演をおこなった。ベルリン滞在中の11月10日、稽古中の少女歌劇団一行は《水晶の夜》を目撃している[4 p.215], [5]。
|
|
| 宝塚少女歌劇団のローマ公演を伝えるニュース映像(1938年12月21日) |
映画の分野でも、この「三国同盟」フィーバーにのって、イタリア、ドイツの映画が積極的に公開された。『リビア白騎隊(Lo Squadrone Bianco, 1936)』『シピオーネ(Scipione, l’Africano, 1937)』『アルプスの槍騎兵(Condottieri, 1937)』 等の広告が映画誌を埋めている。
しかし、日本の都市部の知識階級のあいだで人気があった輸入娯楽は、ハリウッド映画だった。
この時期の日本の映画興行で最大の話題と言えば、おそらく1937年12月に公開されてロングランヒットとなったハリウッド映画『オーケストラの少女(A Hundred Men and A Girl, 1937)』だった。日本の映画ファン、音楽ファンは、人気指揮者のストコフスキーと子役タレント、デュアナ・ダービンにすっかり魅了されて、翌年5月までに全国147館が上映契約を交わしていた。
評判の日比谷映画「オーケストラの少女」を見に行く。成程いゝ。ディアナ・ダービンもいゝが、シナリオのハンス・クレーリーを一ばん賞めたい。
古川緑波 昭和十三年一月十一日
『オーケストラの少女』の上映中、あの日劇の丸い建物を毎日毎日觀客が長蛇の如く列を作つて取巻いたことはイタク各方面を驚かせた。夫がひと月近くも續き、更に日比谷に移つてからも門前市をなす盛況だつたのだから本當に驚く。
「街の經濟線」[6]
海音寺潮五郎:この間「オーケストラの少女」といふの見た。面白かつたね。
武田麟太郎: あれは面白かつた映畫はあそこにいかなきやウソだと思ふね。
「人気作家映画放談会」[7]
われわれは同じものを音楽のばあいにも見出す。「オーケストラの少女」が上映されたあと、ストコフスキーのレコードがパアル・バックの小説のやうに賣れたといふことはどうやら同じ事實を基礎にしてゐるにちがひない。あの映畫が人氣をあつめた當座、喫茶店で若い男たちの注文するレコードが「ハンガリアン狂詩曲」だつたり「椿姫」だつたりしてゐるのは不思議ではない。ひとつの有名な音樂映畫の上映によつて、音楽がイマジネエテイヴに聞かれだしたのではない。むしろ「未完成交響樂」や「オーケストラの少女」にたいするおどろくほどの熱狂といふものが、すでに音樂をイマジネエテイヴに聴かうとする態度のあらはれにすぎなかつたのである。
今村太平[8]
四時すぎてから三人で出て、日比谷へオーケストラの少女を見にゆく。ストコフスキーという者の指揮ぶりを見てハハンと思う。ああいうのは一種のパントマイムであって、あの位の演奏者の技術がなければストコフスキー存在出来ない。あの気どりかた! 一種の大俗物である。かえりに林町へまわりシャケをたべて来る。
宮本百合子 昭和十三年一月一日
だが、この興行の成功が後になって問題視されることになる。
|
|
|
ビクター・レコードの広告
『オーケストラの少女』の人気に乗じてストコフスキーのレコードの販売促進をもくろんだ広告。キネマ旬報 1937年12月11日号
|
美少女と九六陸攻
盧溝橋事件が起きた直後、政府は戦争にともなう財政出動と外貨流出抑制のため、外貨制限を発動した。映画の輸入もその対象となっていた。
内務省はすでに1937年4月に外国映画の検閲手数料を50%も値上げしていたが、日中戦争直後の7月には外国為替管理法と大蔵省令が改正され、輸入映画にも外貨制限が課せられることになった。大蔵省は、外国映画の輸入による外貨流出が年間一千万円近くに達していたことから、8月末から外国映画輸入禁止の措置を採った。禁輸措置は1年余り続き、翌年10月にようやくアメリカ映画に第一次の輸入許可が出た。その内容は、1938年度分として3万ドル・プリント200万尺を許可するが、米大手映画会社日本支社から本国への送金を3年間据え置くというものであった。
古田尚輝 [9]
|
|
|
日本の輸入映画本数の推移(1934~1941)
|
『オーケストラの少女』は、この外貨規制の前にすでに輸入されていた作品で、この対象になっていなかった。それが災いして、1939年に映画法が帝国国会で審議される際に、非難の的になってしまった。
外畫專門館ニテ「アメリカニズム」ニ陶醉シテ時ヲ過ス如キハ、決シテ國民教化ノ善導トハナリマセヌ、實例トシテ明眸皓齒ノ「ディアナ·ダービン」ヲ主役トスル「オーケストラノ少女」ガ一タビ封切セラルルヤ、帝都ノ洋畫「ファン」ハ擧ゲテ熱狂シテ、續映更ニ續映ノ場合ヲ展開シマシタ、是等カラ我ガ日本人ノ得タモノハ何カ、未ダ殘存スル碧眼紅毛ニ對スル依存的思想ト、一本ニ八十万圓也ノ邦貨ヲ米國へ流レ込マシタ國家的損失ノ二ツヲ擧ゲザルベカラザル事實ガアルノデアリマス(拍手)
野口喜一
第74回帝国議会 衆議院 本会議
第23号 昭和14年3月9日
この非難の文言はなかなか示唆的だ。ディアナ・ダービンを「明眸皓齒」と形容しつつ、映画「ファン」が「熱狂」して「碧眼紅毛ニ對スル依存的思想」で「アメリカニズム」に踊らされている、と言う。その結果、「八十万圓」も流出してしまったというのだ。つまり、映画オタクが美少女にうつつを抜かしていたせいで、渡洋爆撃に必要な九六陸攻4機分の金[11]を失ったのだから、国家の一大事である。日本は陸軍も海軍も中国大陸を(そして、その後真珠湾も)攻撃するのに必要な航空機燃料をカリフォルニア産に依存していた[12]。軍も、国民も、カリフォルニア産のものにすっかり依存していたが、国民は我慢しないといけない、ということである。
|
|
|
九六陸攻(九六式陸上攻撃機)二一型
漢口空襲に参加する二一型 (Wikipedia)。
|
外国映画、特にアメリカ映画に対する風当たりが強くなっていた。『オーケストラの少女』が公開される少し前、1937年11月27日の東京朝日新聞に「禍はアメリカ映画゠注目す可き昨年度の出産激減」という記事が掲載されている。これは日本の人口減少(少子化)を嘆く記事で、その原因として「不況の深化に連れて、民衆の経済心理が生殖率を低下させている」、そして「外国映畫等の影響により子供に對して、「非生産的なもの」と云ふ考へ方、アメリカナイズされた、風習」が広がったことを挙げている。この点において、ナチスがアメリカ映画の流入を規制しているのは達見であるともしている。映画評論家の岩崎昶は、この言いがかりのような記事を極めて揶揄的に批評しながら、それでも「未だに萬一をあてにして、楽観してゐる米畫輸入會社も、もう綺麗さつぱりとあきらめるが宜しい」と政府がアメリカ映画への反感をエスカレートさせている状況を見抜いている [13]。この新聞記事が掲載される2日前に日独伊三国で防共協定が締結されている事実も併せて考えると、政府の文化外交政策が硬化することは容易に想像できる。
一方で、日本政府が、防共協定の同盟国であるイタリアやドイツの映画の輸入に関して態度を軟化させたわけでもない。外貨流出の問題は相手がヨーロッパの国でも同じである。東和などの輸入映画商社は規制前に輸入したものを派手な宣伝をかけて上映するよりほかなかった。
その一つがデトレフ・ジールクの『第九交響楽』で、昭和十三年(1938年)に日本で公開されている。奇しくも日本では、『別れの曲』、そして『オーケストラの少女』と、いわゆるクラシック音楽映画が流行していた時期でもあり、東和は「音楽にうるさい」インテリ層をターゲットに『第九交響楽』の宣伝を行っている。広告は、出演者やストーリーよりも、ベルリン歌劇場管弦楽団によるベートーベンの交響曲の演奏の映像が見れる、という点を強調している。
『第九交響樂』は、確によい映畫だと思ひましたストーリーは大した新味感じられませんが一人々々の役者の逹者さは特筆すべき事です。映畫藝術的に云々する事は私のお株ではないので差控へますが、筋に對して「第九」の使ひ方も面白いし、又、この演奏そのものが大いに見、又、聴く値打のあるものだと思ひます。バレーの場面も面白いし、味のある映畫です。決して従来の映畫の様に軽いものではありませんが、それなりに深味と胸に喰入るもののある、感銘を受ける名画だと思ひました。
関 種子 [14]
第九交響楽も亦ナチ獨逸の文化水準を示す異色扁として注目される。内容はベートーヴェンの「第九」をテーマにし一音楽家の藝術と家庭との相剋を、各曲の持つ人間的苦悩を歡喜とに裏づけられたウーファ久し振りの佳作と云はれるが、この中で見るものはクルト・シュレーダー指揮の伯林國立オペラ劇場管絃樂團の出演である。尚、このモデルは名指揮者クルト・ヴェングラーであると云はれるが、我々にはその眞僞の程はわからない[原文ママ]。
卜部晃行 [15]
『第九交響楽』に埋め込まれたナチスのプロパガンダ的要素は、おそらく当時の日本では機能しなかっただろう。ベルリン・オリンピックから2年も経ってしまっており、ラジオの中継実況という技術的偉業はすでに驚きが薄れてしまっていたに違いない。確かに日本も出生率減少の憂き目にあっていて、人口政策立案の必至が叫ばれていたにせよ、ナチスが目指していたような《母性の搾取》とはかなり異質なものだったはずだ。外国映画の観客の大部分を構成する都会の知識人の関心にしても、古典音楽のような高尚芸術にあこがれはあったのかもしれないが、『オーケストラの少女』の熱狂的受容を見る限り、「不遇な父をけなげに支える少女」という当時の日本映画にもありがちな通俗性を兼ね備えていることのほうが重要だったのかもしれない。
卜部は、上に引用した記事のなかで、野村浩将監督『国民の誉(1938)』と交換条件で同じ価格のドイツ、トービス社の映画の輸入が許可された、と述べている。『国民の誉』は国光映画という映画輸入商社が、カメラマンのリヒャルト・アングストとスキー選手のゼップ・リストをドイツから招聘して日本で撮影した作品だ。国光映画社は、イタリアやドイツから反共映画や国策映画を積極的に輸入していたが、過去の伊独共作映画を再編集して防共協定記念映画として売り出すような商魂たくましいところもある。『国民の誉』が、まともなドイツ映画輸入の交換条件となりえたのかは定かではない。
たとえ日独伊三国同盟をもってしても、日本政府にはドイツ映画だけを積極的に輸入する理由もなかったし、余裕もなかった。その後、満州を経由してドイツ映画を輸入することが決まった後も、本数は限られており、実質的には公開されていないに等しい。唯一、大きな衝撃をもって迎えられたのはリーフェンシュタールのベルリン・オリンピック記録映画『民族の祭典』『美の祭典』である。
|
|
|
『第九交響楽』の広告
キネマ旬報 昭和十三年 五月十一日号
|
References
[1]^ 川添紫郎, 飯島正, 内田岐三雄, 清水千代太, “歐洲映畫界土産話,” キネマ旬報, no. 711, pp. 48–53, Apr. 01, 1940.
[2]^ “ヒットラー・ユーゲント派遣團来る,” 寫眞週報, vol. 29, p. 19, Aug. 1939.
[3]^ 高田爾郎, “輕井澤にヒットラー・ユーゲントを訪ねて,” 東宝映画, vol. 1, no. 11, p. 19, Sep. 15, 1938.
[4]^ 大原由紀夫, “小林一三の昭和演劇史.” 演劇出版社, 1987.
[5]^ 衣笠弥生, “論文:演劇をめぐるファシズム期イタリアの文化政策–宝塚少女歌劇団の第一回欧州公演 (1938 年) を通じて,” ディアファネース–芸術と思想, vol. 6, pp. 57–81, 2019.
[6]^ “街の經濟線,” カレント・ヒストリー, vol. 5, no. 5, p. 57, May 1938.
[7]^ “人気作家映画放談会,” 東宝映画, vol. 1, no. 4, p. 4, Jun. 1938.
[8]^ 今村太平, “映画芸術の性格.” 第一芸文社, 1939.
[9]^ 古田尚輝, “映画法施行下の漫画映画,” 成城文藝, pp. 153–125, Dec. 2016
[10]^ 水町青磁, 池田照勝, “三七年度總決算:業界,” キネマ旬報, no. 632, pp. 84–87, Jan. 01, 1938.
[11]^ “昭和14年当時、戦闘機の機体・発動機はいくらだったのか? ―昭和十四年度機体発動機單價交渉經過報告に寄せて,” 専修商学論集, no. 116, pp. 45–68, Jan. 2023.
[12]^ “Japanese Fuels and Lubricants – Article 10 Miscellaneous Oil Technology and Refining Installations,” U. S. Naval Technical Mission to Japan, X-38(N)-10, Feb. 1945.
[13]^ 岩崎昶, “アメリカ映畫と出産率,” キネマ旬報, no. 631, p. 9, Dec. 11, 1937.
[14]^ “映畫「第九」のメモ,” スタア, vol. 6, no. 17, p. 31, Sep. 1938.
[15]^ 卜部晃行, “外國映畫時評,” 映画と音楽, vol. 2, no. 6, p. 68, 1938.
KINOMACHINAをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。