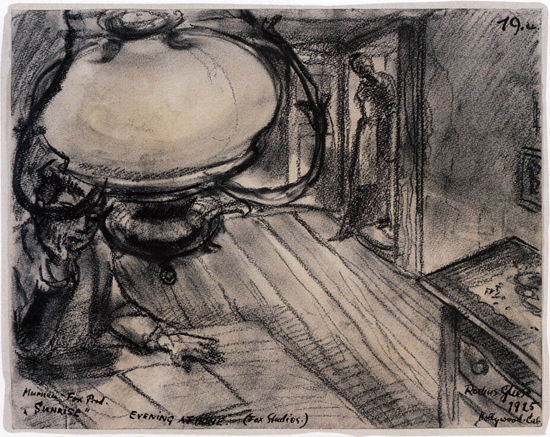|
| フレデリック大帝(1921-22)
|
フレデリック大帝
Fridericus Rex
アルゼン・フォン・クセレピィ 監督
Arzen von Cserépy
オットー・ゲビュール、アルベルト・シュタインリュック、エルナ・モレナ 出演
Otto Gebühr, Albert Steinrück, Erna Morena
ギード・ジーベル 撮影
Guido Seeber
アルゼン・フォン・クセレピィ、ハンス・ベーレント、ボビー・E・リュトケ 脚本
Arzen von Cserépy, Hans Behrendt, Bobby E. Lüthge
クセレピィ・フィルム 製作
Cserepy Film Co. GmbH
UFA 配給
Universum Film (UFA)
これは、1921年から1922年にかけて製作された4部作です。全290分。
第一部 疾風怒濤 (Sturm und Drang)
第二部 父と息子 (Vater und Sohn)
第三部 サンスーシ (Sanssouci)
第四部 運命のいたずら (Schicksalswende)
この映画は、ウーファ史上初めて「政治的問題作」として話題になった作品です。1922年の3月にベルリンのウーファ・パラスト劇場で第一部「疾風怒濤」が公開されたとき、ウーファは、プロシア軍人の服装をさせた男たちをパレードさせるなどかなり過激な宣伝を行いました。この映画の国粋主義的な香りとウーファ設立のいきさつが相俟って、国内の左翼陣営を刺激することになったのです。
ウーファはもともと第一次世界大戦中の1917年、プロパガンダ映画製作を主な目的として、ドイツ銀行が主体となって設立された国策会社です。それが大戦後の1921年に民営化され、ウーファは「共和国的な」 ーすなわち大衆の好みに迎合的なー 性格を帯びるようになります。この時期の有名な作品として、フリッツ・ラングの「ドクトル・マブゼ(1922)」ディミトリ・ブコウスキーの「ダントン(1921)」などがありますが、暗い世相を反映した犯罪者や、歴史スペクタクル、室内劇、社会派ドラマなど、広いテーマを扱っていました。当時のドイツ国内は、その後のヒンデンブルグなどに代表される「帝国派」と社会民主党などに代表される「人民派」に大きく二分されていました。そのどちらに与するともなく、大衆娯楽を提供するのがウーファだと思われていました。ところが、「フレデリック大帝」は、かつてのプロイセン帝国の栄光を賛美し、フリードリッヒ二世を英雄として描いていたのです。明らかに「帝国派」 ーかつてのドイツの栄光を取り戻すー のスタンスの映画です。リベラルの「ベルリナー・ターゲブラット」紙は検閲による上映中止を求め、社会民主党系の「フォアヴェルツ」紙は映画のボイコットを呼びかけました。
しかし、この映画は大ヒットし、皮肉にもその後「プロイセン映画」と呼ばれる一連のジャンル映画を作ることにもなったのです。この映画を含めたプロイセン映画のほとんどで、オットー・ゲビュールが大帝を演じています。最も有名なのは1933年の「Der Choral von Leuthen」です。もともと、プロイセン映画が描いていた保守性と、ナチスの思想は必ずしも相容れなかったのですが、愛国精神の鼓舞という点で非常に使いやすい道具であったのは間違いありません。
この映画の製作したクセレピィ・フィルムは、歴史映画を得意としており、舞台俳優から映画監督に転身したラインホールド・シュンツェルが「マグダラのマリア(1919)」「キャサリン大帝(1920)」などのヒット作を作っていました。「フレデリック大帝」は、アルゼン・フォン・クセレピィ自身が監督した大作です。時代考証が重んじられ、フリードリッヒ・ジーブルグ博士なる人物を呼んで、帝国軍の制服からサンスーシの内装にいたるまで正確に復元されたようです。原作はヴァルター・フォン・モロ、「野卑で、下品な国粋主義者ばかりが出てくる作品」と一部ではけなされていましたが、その後も多くのプロイセン映画が下敷きにしています。
「フレデリック大帝」の上映は、政治闘争の舞台となります。社会民主党や共産党は、「このゴミを上映する映画館は反動的だ」と非難し、上映する映画館は警察の警護を必要としました。しかし、民衆の大多数はこの大作を歓迎し、ベルリンのウーファ・パラストは定員2000人の2倍、3倍の超満員の上映が続きました。映画評論家ハンス・フェルドによれば(1)、
この大衆の熱狂的な人気に(左派が)まともに闘っても勝ち目はなかった。この少数反対派ができることと言えば、歴史的知識に乏しい観衆を混乱させることくらいであったが、これはベルリンなどの大都市のプレミア上映では効果があった。必要なのは(18世紀の)軍服の知識とすばやい反応神経だけ。オーストリア軍、ロシア軍、フランス軍が、スクリーンに登場したら、すぐに拍手大喝采をするのだ。知識に乏しいほかの観客はつられて喝采する。敵に攻め込まれてプロシア兵が退却しているのを拍手して喜んでいたと愚か者たちが気づくのは、字幕が出てきてからだ。
Hans Feld
結局、ウーファにとっては「売れるもの」であれば、それが帝国派の反動的な映画であっても、インドの神秘的な伝説であっても、犯罪地下組織のアクションであっても、なんだってかまわなかったのが本当のところです。
Reference
(1)Klaus Kreimeier, “UFA Story: A History of Germany’s Greatest Film Company, 1918 – 1945”