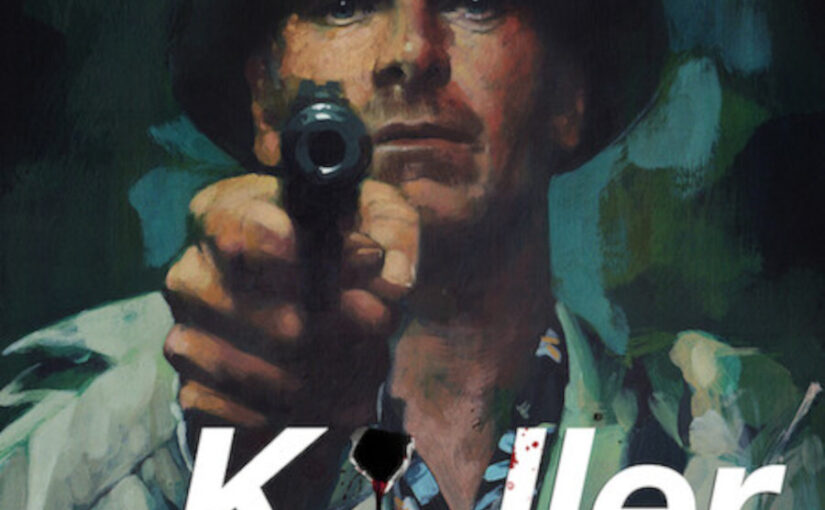映画作りについての映画
Dazedのニック・チェンは新作『ザ・キラー(The Killer, 2023)』についてのインタビューが終った後、デヴィッド・フィンチャーにこう尋ねた。
「これって映画作りについての映画ですよね?」
虚を突かれたのか、フィンチャーは否定しなかった。
スナイパーというのは、達成したいことについて、必定の知識を持ち合わせていなければならない。多くの特化されたテクノロジーに依存しているし、見返りも大きい。しかもチャンスは1回限り。うん、確かにある意味では、たぶん…
安っぽい心理学だけどね。
DAVID FINCHER [1]
この作品に対する評価は全般的に生温く、Netflixでも話題になったとは言えない。プロフェッショナルの殺し屋(マイケル・ファスベンダー)が主人公のスリラーと聞いて、多くの人が「ジョン・ウィック」や「キングスマン」「ジェイソン・ボーン」シリーズを期待したのかもしれないが、平均よりもマシな程度のアクションと、説得力のない設定に、どうも拍子抜けしてしまったようだ。私も、実はもう少しエキセントリックなものを期待していたのだが、ファスビンダー演じる殺し屋の服装のような、退屈で、ねずみ色で、さえないプロットにむしろ驚いた。古典的な映画では、プロの殺し屋と言えば、『サムライ(Le Samouraï, 1967)』や『ジャッカルの日(The Day of the Jackal, 1973)』のような無口で無表情な男を造型してきた。確かにマイケル・ファスビンダー演じる殺し屋は無口で無表情だが、頭の中でずっと喋っている。最初の20分を見ればわかることだが、これは予期もしなかったどんでん返しで話題をさらったり、新しいヒーロー・シリーズを狙って作られたものではない。どうしたら、この薄っぺらい哲学をずっと頭の中で繰り返している男の頭の中に、観客を引きずり込むことができるか ── 問題はそれを多くの観客がたいして面白いとは思わなかったことなのだが ── それを挑戦した映画なのだ。
冒頭の20分
ここでは、映画の冒頭、20分あまりの部分だけを考えてみたい。つまり、殺し屋がパリで暗殺に失敗して飛行機で逃亡する直前までだ。
ファスビンダー演じる殺し屋は、パリに住む、ある裕福な男を暗殺するよう依頼を受けている。彼は、標的のアパルトマンの向かいのビルにあるweworkの空きオフィスに侵入し、そこで暗殺の機会をうかがっている。何日も待つあいだ、彼は望遠鏡で向かいのアパルトマンの周辺をくまなく観察し、ヨガで身体を整え、マクドナルドで買ったエッグマフィンのマフィンを捨ててタンパク質だけを摂取する。サウンドトラックは、パリの街中の環境音、殺し屋が時々ヘッドフォンで聞くザ・スミスの音楽、そして彼の内的独白(interior monologue)で埋められる。この内的独白で、殺し屋は自分の仕事の哲学を語る。
Stick to your plan. Anticipate, don’t improvise. Trust no one. Fight only the battle you’re paid to fight.
計画通りやれ 予測しろ 即興はよせ 誰も信じるな 対価に見合う戦いにだけ挑め
The Killer (2023)
『ザ・キラー』では、編集のルールは極めて明確だ。殺し屋の一人称ショット(以下、POVショット)では、彼自身が聞いている音そのものがサウンドトラックとなるのに対し、殺し屋をカバーする(殺し屋が写っている)ショット(以下、カバレージショット Coverage)では、そのカメラの位置で聞こえるであろう音と殺し屋の内的独白がサウンドトラックとなる。重要なことは、POVショットでは内的独白は聞こえない(ある1カ所を除いて)。例えば、殺し屋がヘッドフォンを右耳だけに差し込んで、窓から地上のカフェを見下ろすシーンを見てみるとよい。彼の視点から見たカフェの様子のPOVショットでは、環境音を背景にザ・スミスの「Meat Is Murder」が右のスピーカーからのみ聞こえる。一方、カットが入って、彼をとらえたカバレージショットのときには、ザ・スミスの音はヘッドフォンからの漏洩音になり、内的独白がそれを覆うように支配する。
彼のPOVのときには、彼が聞いている音楽が音響空間を占領し、大音量になる。だが、一方で彼の内部での独り言もある。それが大音量のスミス、それから彼の姿とボイスオーバーのための空間、というパターンに出来上がったんだ。こういった音との垂直編集をやっていたんだ。
Kirk Baxter[2]
大音量のザ・スミスの音楽が支配するPOVショットと殺し屋の内的独白のカバレージショット往復するパターンは、最初に前述のカフェを見下ろすシーンで、まず提示されるが、これは、暗殺の実行シーンのために準備されたものである。暗殺のシーンでは、ザ・スミスの「How Soon Is Now」の大音量が支配するスコープのビュー(殺し屋のPOVショット)と、「完璧な殺し屋の哲学」を語るモノローグとライフルを構える殺し屋のカバレージショットが交互に切りつなげられていく。そしてトリガーを引く瞬間が接近するにつれ、ショットの長さは急激に短くなっていく。上がってはいけない脈拍がどんどん上がっていくような感覚だ。
『ザ・キラー』が一般の観客のあいだで高い評価を得ていない[❖ note]❖観客の評価 例えばRotten Tomatoesでの批評家の評価は85%に対し、観客の評価は61%(2025年12月)と大幅に低い。「ジョン・ウィック」シリーズが批評家/観客のあいだで評価に大きな差がないことと対照的だ。理由の一つに、この内的独白のなかで語られる哲学と、実際に殺し屋の行動が一致していないことが挙げられる。多くの感想が、「この殺し屋は、たいそうなことを言うわりに、まったく準備ができていない」ということを指摘している。暗殺計画が失敗しているものだから、素人でも「プラン」なるものの穴をたくさん見つけて、面白くないと難癖をつけることが可能だ。だが、フィンチャーの映画で、そもそも21世紀の映画で、主人公の行動と言葉(思想)が一致していないからつまらない、というのは批判として成り立ちにくい。そんな映画はごまんとあるからだ。むしろ、多くの人が感じているのは、主人公の行動と言葉が一致していないという物語の見せ方がつまらない、ということなのではないか。つまり、脚本と、それを実現した、演出、編集のルールに同調できない人が多いのではないだろうか。
|
|
|
『ザ・キラー(The Killer, 2023)』トレイラー
Netflix
|
Le Tueur
原作はフランスのアレクシス・マッツ・ノラン(Alexis “Matz” Nolent, 1967-)作、リュック・ジャカモン(Luc Jacamon, 1967-)画のバンドデシネ「Le Tueur(英題 The Killer)」で、1998年に初巻が発売されて以来13巻が発表され、スピンオフも2023年まで発表され続けてきた人気シリーズだ。私は第1巻の「Long feu」を英語版で読んだだけであるが、映画『ザ・キラー』の第1章は、この第1巻を元にしていると思われる[3]。
|
|
|
“Le Tueur (The Killer)” の第1巻 “Long feu”
デヴィッド・フィンチャー監督『ザ・キラー(The Killer, 2023)』はこのバンドデシネを原作としている。© Casterman
|
映画と同じように、アパートの1室でスナイパー・ライフルを片手に、なかなか現れない標的をじっと待っている。だが、映画に比べて、この原作コミックの殺し屋のキャラクターは、さらに内的独白が多く、極めて饒舌である。その長い待ち時間の中で、今までの「仕事」や、この稼業をどうやって始めたかを回想しながら、自分の《哲学》を語っている。「誰からも命令を受けない、誰にも報告しない、俺の動機はただひとつ:金だ」「人間らしく生きろ、豚やゴキブリのようではなく」といった、どこで定型化したのか出所不明のアフォリズムが次から次へと登場する。原作では、殺し屋は、もっと具体的に人間への不信、シニシズムを露わにする。ミルグラムの実験や第101警察予備大隊に言及し、人間が本質的に自己中心的で殺戮を好む存在であるというテーゼを繰り返す。これらの回想や思考は、テキストと同時にデフォルメされた画で示されていく。殺し屋自身が行った殺人と、歴史上の殺戮が同じ平面で画像化されて、その上に、殺し屋のモノローグがテキストのレイヤーでナレーションのように強化していく。マッツ/ジャカモンは、このような強迫的な思考と回想の視覚的な繰り返しによって、絶望と無知から生まれたシニシズムの渦に自ら巻き込まれて、そこから抜け出せなくなった殺し屋を造型していく。自殺願望やラストの破壊は、それらの帰結に過ぎない。
『ザ・キラー』:脚本
『ザ・キラー』の映画化の話は2007年ごろからフィンチャーの周辺で進んでいた[❖ note]❖映画化の難航 最初に映画化を検討したのはパラマウントとブラッド・ピットだった。その際にはアレッサンドロ・カモンが脚本を準備し、デヴィッド・フィンチャーにも脚本が渡されていた。2015年に再度映画化の話が浮上した時、フィンチャーがウォーカーに脚本を依頼した[4]。。脚本を担当したアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーは、内的独白で物語が進んでいく原作のスタイルを踏襲しているが、殺し屋の思考や態度を大きく変え、表現手法も内的独白の言葉のみに集中し、形容詞や副詞をできるだけ排した極めて短いセリフで物語を構築した。過去や具体的な事件には言及せず、視覚的なフラッシュバックやインサートも使用しなかった。この脚本は、殺し屋に「人間は所詮残酷な生物だ」といった逃げ道を与えず、究極の虚無主義のマントラを復唱させる。
I serve no God or country. I fly no flag. If I’m effective, it’s because of one simple fact: I Don’t Give A Fuck.
俺は神にも国にも仕えない 誰も代表しない 成功の秘訣はごく単純 ど…う…で…も…いいだ
The Killer (2023)
ウォーカーは、断片的な思考の羅列で、意識の流れ Stream of Consciousnessの内的独白をすすめていく。「それは誰が言ったんだっけ」といったような言葉が差し込まれ、論理的なつながりのないセリフが、ただ連なって自然に話が進む。
“Do what thou wilt shall be the whole of the law.” To quote… someone; can’t remember who.
The Killer (2023)
Skepticism is often mistaken for cynicism.
Most people refuse to believe that the Great Beyond is no more than a cold, infinite void… but I accept it.
The Killer (2023)
これは殺し屋の頭のなかで迷走している言葉の流れであって、何かを提示する言葉ではない。だから、始終繰り返される「予測しろ 即興はよせ」という言葉も、殺し屋が自分に言い聞かせている言葉だと解釈するのが妥当なのではないか。殺し屋は自分が「完璧な殺し屋」だと、暗示をかけるように心の中で反芻しているのだ。
内的独白
映画で使われているボイスオーバーには、三人称のナレーション third-person narrator と一人称のナレーション first-person narrator とがある[❖ note]❖ボイスオーバー ボイスオーバー、特に内的独白のハリウッド映画での成り立ちについては拙著「FILM NOIR REVIEW」のVolume 1『三階の見知らぬ男』の章に詳述したので、参考にしていただきたい。。三人称のナレーションとは、劇中の人物ではなく、外部の誰かが中立的な位置から語るものである。『裸の町(The Naked City, 1948)』のオープニングで、プロデューサーのマーク・ヘリンジャーが「この裸の町には800万の物語がある これはそのひとつだ」と宣言するのは、三人称ナレーションの最も有名な例だ。一人称のナレーションとは、劇中の人物が語るものである。その中でも、話者が観客を相手に語りかけているもの(『我等の町(Our Town, 1940)』『フォレスト・ガンプ(Forrest Gump, 1994)』)、劇中の別の人物に語りかけているもの(『ブロンドの殺人者(Murder, My Sweet, 1944)』『小さな巨人(Little Big Man, 1970)』)、そして自らの心の中で語っているものがある[❖ note]❖媒体を介したナレーション 手紙やノートから発せられるナレーション、またはテープやビデオ、コンピューターなどの録音装置に語りかけるナレーションの形式もある。誰かにあてた手紙や録音である場合が多いが、内的独白に接近する。極めて早い時期の一人称ナレーションの例である『深夜の告白(Double Indemnity, 1944)』は主人公のネフがディクタフォンに語りかけている。。この最後のものが内的独白 interior monologue になる。
映像作品での一人称のナレーションをどう扱うかは、実はつかみどころのない問題だ。ボイスオーバーというテクニックをまがいものと判ずる映画人や批評家も多いし、観客もその自意識過剰な演出を嫌う場合が多い。ハリウッド映画のボイスオーバー手法は、ラジオドラマを追従するように発展してきた。ハリウッド映画を見渡すと、1930年代にはボイスオーバーを使用した映画は数えるほどしかない。ところが、同時代のラジオドラマが積極的に一人称のナレーションを実験し、さらには「ジョニーは戦場に行った(Johnny Got His Gun)」という内的独白の極北のようなラジオドラマが成功したことは、ハリウッドの映画製作に大きな影響を与えた。1940年代に、いわゆるフィルム・ノワールで様々な様式のボイスオーバーが試行され、特に内的独白はフィルム・ノワールのクリシェになるほど、映像のスタイルと深く連関した手法だった。
内的独白は、その演出、特に音響の扱い方が重要なカギになってくる。ハリウッド映画で最も早い時期に内的独白に挑戦した『三階の見知らぬ男(Stranger on the Third Floor, 1940)』では、当時まだ新しいテクノロジーだったリレコーディングやエコーを駆使して独特の音響世界をつくりだしている。『ザ・キラー』は前述したように、明確なルールに従って映像・音響演出が行われている。だが、視覚と聴覚のあいだの演出にズレがうめこまれていて、観客は殺し屋の世界に没入できないのではないか。
視覚/聴覚/セリフ
『ザ・キラー』では没入感の破綻がどうして起きているのか。それを理解するためには、冒頭の20分のシーンについて、映像、音響、セリフに分離して、それぞれ考えてみる必要がある。
ナラトロジーの分類に基づいて、語り手と語られる物語の関係と、語り手の物語に対する位置とを整理しておく[5]。
まず、語り手が自分自身の物語を語っているかどうかで分類する。
-
ホモダイエジェティック homodiegetic 自分自身の物語を語っている
-
ヘテロダイエジェティック heterodiegetic 自分以外の物語を語っている
そして語り手はどこにいるかで分類する。
-
イントラダイエジェティック intradiegetic 語り手は物語の中にいる(物語の登場人物)
-
エキストラダイエジェティック extradiegetic 語り手は物語の外側にいる(登場人物ではない)
これは、テキストで書かれた物語における分類であって、これをいきなり映画の物語話法に適用しようとすると破綻してしまう。「語る」という行為と、「見る」「聞く」という行為は同質ではないからだ。ここでは、映像においては、カメラはカメラの視点の人物の物語をとらえているか/視点以外の物語をとらえているか(ホモ/ヘテロ)、カメラは登場人物の視点か/登場人物の視点ではないか(イントラ/エクストラ)[❖ note]❖カメラの物語 カメラが主人公のPOVでないにもかかわらず、登場人物の視点である場合(ヘテロダイエジェティック/イントラダイエジェティック)もある。例:『ありふれた事件(C’est arrivé près de chez vous, 1992)』、音響に関しては、物語内の音か/物語外の音か(ダイエジェティック/ノンダイエジェティック)、もしダイエジェティックな音の場合、それを聞いているのは登場人物か/登場人物ではないか(イントラ/エクストラ)というかたちで分類した。セリフに関しては、内的独白の場合は、自分自身の物語/他人の物語を語っているか(ホモ/ヘテロ)、語り手は物語の中にいるか/外にいるか(イントラ/エクストラ)で分類する。セリフが複数人の会話(手紙のやり取りなどを含む)場合は、会話が物語の中の登場人物同士なのか/物語に登場していない人物にあててなのか(イントラ/エクストラ)という考え方が成り立つだろう。
この分類に従って、『ザ・キラー』の冒頭20分を分解するとどうなるか。
| A(POV) | B(Coverage) | |
| 映像 Visual | 主観 ホモダイエジェティック イントラダイエジェティック | 客観 ヘテロダイエジェティック エクストラダイエジェティック |
| 音響 Sound | 物語世界内+主観 音の発生源:ダイエジェティック 音の聴取:イントラダイエジェティック | 物語世界内+客観 音の発生源:ダイエジェティック 音の聴取:エクストラダイエジェティック |
| セリフ Speech | 内的独白 ホモダイエジェティック イントラダイエジェティック |
上の表の分類は、ほぼ大部分のショットに当てはまるが、映像と音響に関しては、いくつかの例外[❖ note]❖例外のショット A(POV)ショットのうち、殺し屋の視野と完全に一致しているものと、疑似的なものが存在する。音響上、ノンダイエジェティックな音楽が低く流れているシーンが2カ所、セリフについてもヘテロ/イントラダイエジェティックになるシーンが2カ所ある。またセリフでも2カ所、電話のシーンと暗殺失敗後の「Fuck」はヘテロダイエジェティックな位置になるだろう。がある。そういった例外は特に珍しいことではない。ここで注目したいのは、内的独白である。内的独白はBショットにのみつけられている。これは、執拗に一貫性を維持している。そして、上の表からも分かるように、Bショットは映像と音響はヘテロ/エクストラダイエジェティックなのに、そこにホモ/イントラダイエジェティックな内的独白が重ねられることになる。一般的には映像、音響ともにホモ/イントラダイエジェティックなAショットのほうに内的独白をつける方が親和性が高いはずなのに、あえてずらしているのだ。
この意図的な違和が、語り手である殺し屋と観客の距離を非常に居心地の悪いものにしている。
信頼できない語り手
もうひとつ、『ザ・キラー』の物語で重要なのは、殺し屋はいわゆる「信頼できない語り手 unreliable narrator」という点である。
「信頼できない unreliable」にもいろんな意味があるが、『ザ・キラー』の語り手は意図的に聞き手(観客)を欺こうとしているわけではなく、むしろ彼自身の認識の歪みが、その言葉を歪めて信頼できないものにしてしまっている [4]。『ザ・キラー』の物語としての仕掛けを考えていると、やはり「信頼できない語り手」の物語として有名な、カズオ・イシグロの小説「日の名残り(The Remains of the Day)」をどうしても想起してしまう[6][7]。
「日の名残り」のスティーブンスも、『ザ・キラー』の殺し屋も、長年やってきた自分の職業(執事/殺し屋)に関しては誇りがあり、自分にはそれを語る資格があると思っている。どちらの物語も、話が展開するにつれ、読者/観客はあることに気づいていく。彼らの誇りは実は多分に独りよがりで、彼らが言う「完璧な執事/殺し屋」は視野狭窄的な思考の末の袋小路のように感じられてくるのである。
スティーブンスは「偉大な執事」とは何かを執拗に考え続ける。ダーリントン卿の失墜とともに失われた彼のプライドを埋め合わせるために捏造された概念だと言ってよいだろう。主人を切り離して、機能としてだけの執事という概念にこだわるスティーブンスは、《執事のカリカチュア》となっていく。《カリカチュア》という点においては、『ザ・キラー』もおなじだ。ファスビンダー演じる殺し屋は、肥大化した完璧主義と秘密主義の意識(あくまで意識であって、実態ではない)に支配されており、まさしく《プロの殺し屋のカリカチュア》である。
映画『ザ・キラー』では、殺し屋をカバーするショット(Bショット)の客観的観察が、カリカチュア化を増幅する。殺し屋は、自分では「ドイツ人の観光客」になりすましているつもりでパリの舗道でスマートフォンを踏みつぶし、マクドナルドのエッグマフィンでタンパク質を10グラム摂取し、いつも脈拍数をモニターしながら行動し、おそらく塩素系液体の入ったスプレーを3回吹いて自分の痕跡を消したつもりになっている。逃走に使うために準備しているのが電動ヴェスパだというのも、ジョークのように思えてくる。そして、最もクリティカルな瞬間が訪れたときに、彼が精神集中のために使うのがザ・スミスである。スコープが標的をとらえた瞬間、モリッシーが「I am human and I need to be loved」とクネっている。
『ジョン・ウィック』のキアヌ・リーヴスが、バケットハットをかぶって、アマゾンばっかり使って、ついドイツ人を差別するようなことを口走って、それでザ・スミスの、しかも「How Soon Is Now」が好きな、そんなソシオパスだとを思ってくれればいい。
David Fincher Link
『ザ・キラー』においても、「日の名残り」においても、物語のクライマックスで、語り手の欺瞞を鏡のように反射するのが、女性だという点も興味深い。スティーブンスの寂莫とした後悔は、ミス・ケントンとの会話によって映し出されていく。黙りこくった殺し屋が聞くのは、エキスパート(ティルダ・スウィントン)の熊と猟師のジョークである。読者/観客は、女性たちの言葉による反射によって信頼できない語り手の物語世界での存在位置を確認する。もちろん、信頼できない語り手本人たちが、どう感じているのかは不明だ。
コミットメント
カズオ・イシグロの「日の名残り」の主人公、スティーブンスと、『ザ・キラー』の主人公の殺し屋は、肥大化したプロフェッショナリズムにぽっかり穴が空き、危機を迎える。スティーブンスは仕えていたダーリントン卿を失い、彼のプロフェッショナリズムを支えていた枠組みを失ったことが発端だ。殺し屋のほうは、暗殺に失敗した報いとして、消されそうになり、その過程で自分のパートナーが重傷を負うことがきっかけである。「日の名残り」では、スティーブンスのコミットメントが外側から揺るがされることが原動力なのだが、『ザ・キラー』はそこが違う。殺し屋ははっきりと宣言している。「I Don’t Give A Fuck ど…う…で…も…いい」── 彼は自分は何にもコミットしていないと思っているのだ。国にも、正義にも、友情にも、愛情にも、法にも、コミットしていない。おそらく金についてでさえ、それほどコミットしていない ── と思っている。
究極のギグワーカーである殺し屋が仕事場として使っている空きオフィスのドアガラスに「wework」の文字が反転して見えている[❖ note]❖wework 『ザ・キラー』の撮影が行なわれたのは2021年11月から2022年3月だが、この時期にはweworkの財務トラブルは広く知られていた。。がらんとしたオフィスの色彩が、乾いてくすんでいる。ギグエコノミーの空騒ぎの末に、たどりついた虚無的な2023年の風景としてふさわしいものだろう。世のギグワーカーはみんな心の中で言っている ──「I Don’t Give A Fuck ど…う…で…も…いい」。もはやギグワーカーだけではない。自分は自分だけにコミットしている、それ以外はただの変数にすぎない ── そう思っている人は多い。だが、この I-Don’t-Give-A-Fuck-World はすがすがしい解放と自由を約束したはずなのに、なぜこんなに憂鬱なのか。そのパラドックスを『ザ・キラー』は描こうとしている。成功しているかどうかは分からないが、《憂鬱》を浮き出させる手法として「ズレた内的独白」が使われたのだ。
カズオ・イシグロの小説は終始一人称だったが、映画版『日の名残り(The Remains of the Day, 1993)』は一人称による独白ではなく、三人称のカメラによって、スティーブンスが思考の袋小路でたたずむ様子を描いていた。ボイスオーバーはミス・ケントンとスティーブンスのあいだの手紙のやり取りに限られ、過去の追想は三人称カメラによるフラッシュバックとして描かれる。哀しく、寂莫とした袋小路ではあったが、原作小説の一人称叙述が読者に強いるような痛みは伴っていなかったように思う。映画『日の名残り』は、様式的な妥協だった。観客の想像力を信じたうえで、スティーブンスの内的独白をあえてナレーションにしなかった。妥協をしてでも、様式の端正な一貫性が尊重された前世紀の映画である。
コロナ禍を通過した世界、この I-Don’t-Give-A-Fuck-World では、様式の端正さは滅亡こそしていないが、贅沢品になってしまった。ここでは、過剰なまで《私のことば》が氾濫し、外へ染み出している。『ザ・キラー』の内的独白は、X、Instagram、FacebookといったSNSから、YouTube、ブログ、ニュース記事などありとあらゆるウェブサイトに装備されているレビュー、コメント、返信といったたぐいの場所でみられる、《私のことば》の氾濫の相似形にすぎない。いわゆる《プラットフォーム》は、そこで起きることを常に平静に眺めているヘテロダイエジェティックなエージェントであり、決してそこで起きていることに参加しないエクストラダイエジェティックなものである。そこにひたすら、《私のことば》が書き連ねられている。
かつて、私はアマゾンである書籍のレビューを読んでいて、ひどく面食らったことがある。書籍のレビューというよりは、持論の展開といったものだった。そのレビューの書き手のアイコンをクリックして、その人物がほかの書籍や商品にどんなことを書いているのか読んでみた。日用品であろうと、雑誌であろうと、電子機器であろうと、この人物の《私のことば》の氾濫は、とめどなく広がっていた。その言葉は本人にとっては心地よいものなのであろう。しかし、それを読む者は、この人物の眼孔に自らの眼球を埋め込まれて、強制的に世界を眺めさせられているような耐え難い苦痛にさらされる。アマゾンというヘテロ/エクストラダイエジェティックな空間で、「意識の流れ」のような、まとまりのない、思いつきの言葉の羅列にすぎない内的独白を聞かされている気分になる。『ザ・キラー』の内的独白を聞かされているとき、私はこのアマゾンのレビュアーのことを思い出した。
ファスビンダーの「I Don’t Give A Fuck ど…う…で…も…いい」と言うセリフは、内的独白のなかでも、そこだけ音響が違っていて際立っている。彼は、プロフェッショナルの殺し屋のカリカチュアであり、ギグワーカーのカリカチュアであり、大義にコミットせずに冷笑をオンラインでつぶやく者たちのカリカチュアである。そんなカリカチュアを、カリカチュアされている者の視点から描いても、当然共感を呼ぶものにはなりにくい。だが、本来、共感なんて映画に必要だったのか。
「エキスパート」が語る熊と猟師のジョークを、殺し屋は黙って聞く。私たち観客は、彼がどんな感想を持ったのか知らない。殺し屋は口元にかすかに微笑を浮かべただけだった。自身が滔々と語るプロフェッショナリズムに対する、唯一の返信に、彼は答えなかった。このグロテスクな沈黙が、サイレンサー銃による殺しによって終わるというやりきれなさが、どこまで行っても救いのない I-Don’t-Give-A-Fuck-World の風景なのかもしれない。
Notes
デビッド・フィンチャー監督の『ファイト・クラブ(Fight Club, 1999)』は、1回目の視聴とその後の視聴で、ダイエジェシスが変化する作品である。
| 1回目の視聴 | 2回目の視聴 | |
| 映像 Visual | 客観 ヘテロダイエジェティック エクストラダイエジェティック | 主観 ホモダイエジェティック イントラダイエジェティック |
| 音響 Sound | 物語世界内外+客観 音の発生源:ダイエジェティック+ノンダイエジェティック 音の聴取:エクストラダイエジェティック | 物語世界内外+主観 音の発生源:ダイエジェティック+ノンダイエジェティック 音の聴取:イントラダイエジェティック |
| セリフ Speech | 会話 イントラダイエジェティック | 内的独白(+会話) イントラダイエジェティック |
References
[1]^ N. Chen, “David Fincher on Filmmaking and His Twisted New Comedy, The Killer,” Dazed, Nov. 06, 2023. Link.
[2]^ “‘The Killer’: DP Erik Messerschmidt, Editor Kirk Baxter & Sound Designer Ren Klyce On ‘The Joy’ Of Working With David Fincher – Contenders London,” Deadline, Oct. 07, 2023. Link.
[3]^ “Casterman – Le Tueur – Tome 1 – Long feu.” Link.
[4]^ D. Fear, “How David Fincher Turned ’The Killer’ Into a Mean, Lean Punch to the Gut,” Rolling Stone Magazine, Nov. 08, 2023. Link.
[5]^ G. Prince, “A Dictionary of Narratology.” U of Nebraska Press, 2003.
[6]^ A. Parkes, “Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day: A Reader’s Guide.” Bloomsbury Publishing USA, 2001.
[7]^ K. Wall, “”The Remains of the Day” and Its Challenges to Theories of Unreliable Narration,” The Journal of Narrative Technique, vol. 24, no. 1, pp. 18–42, 1994
KINOMACHINAをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。